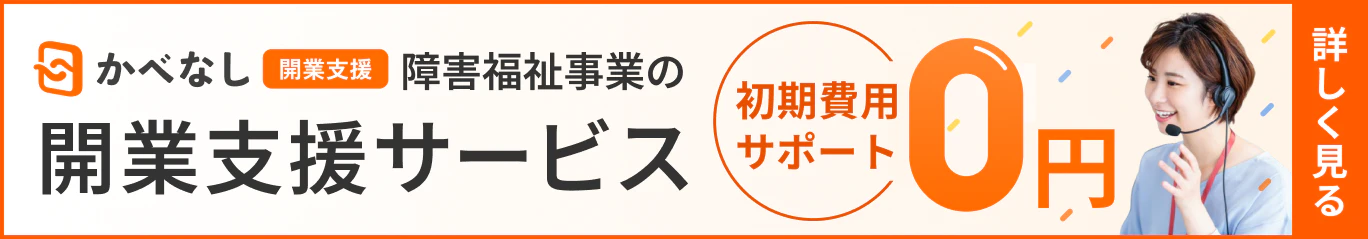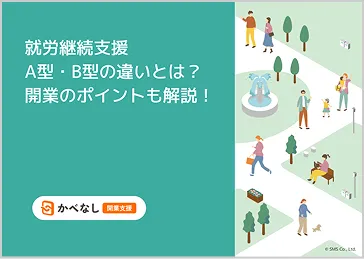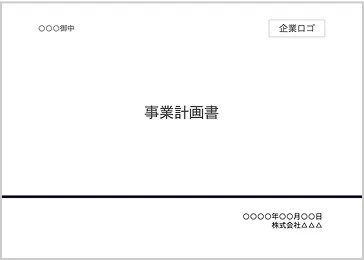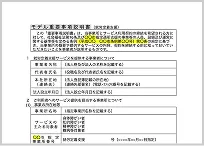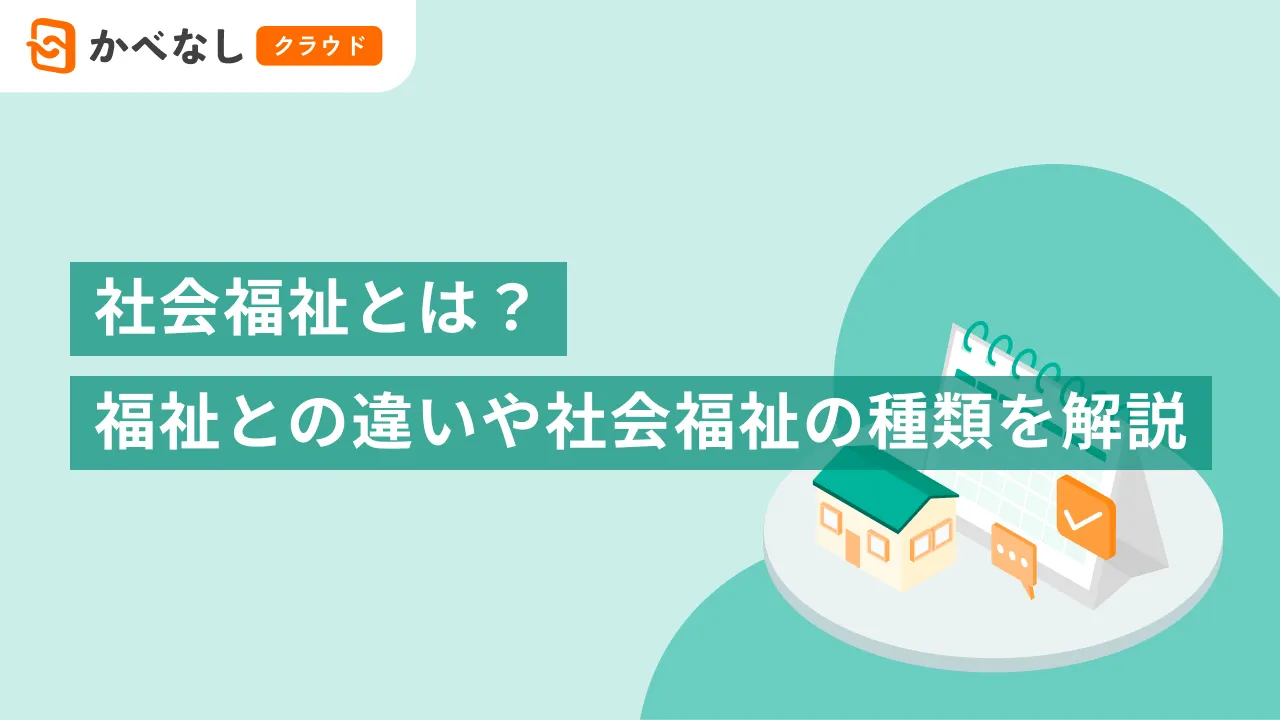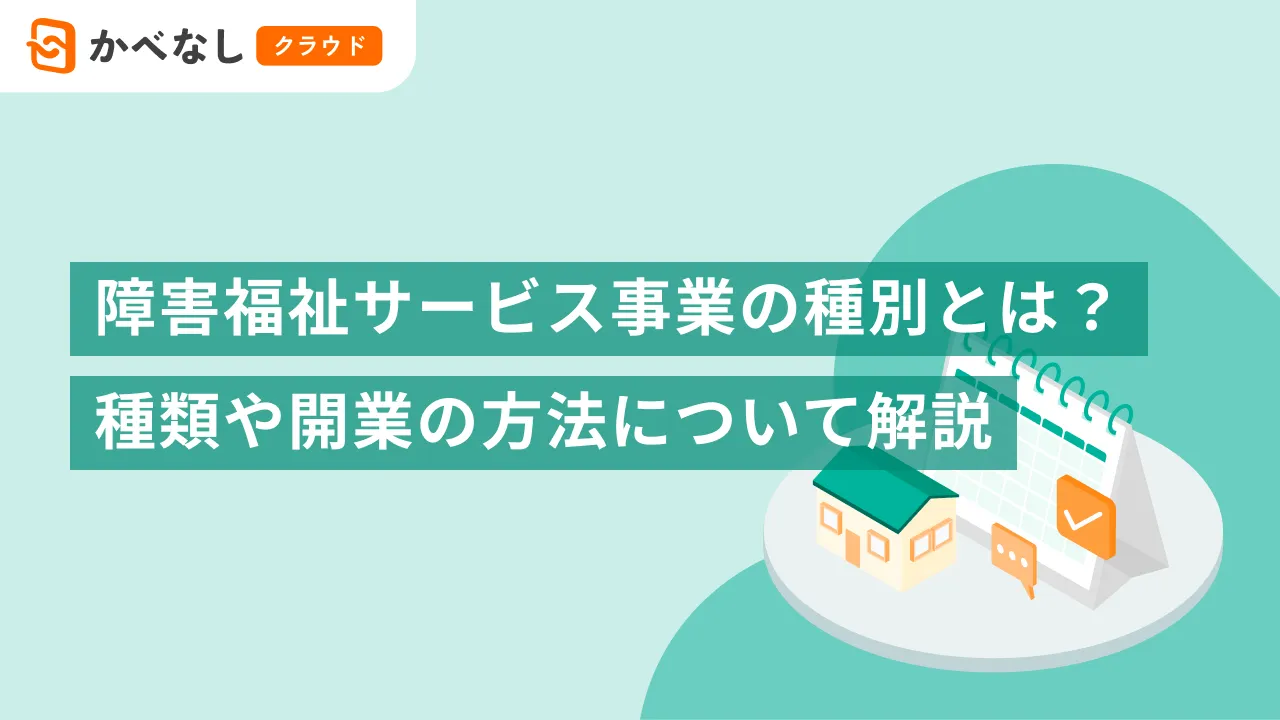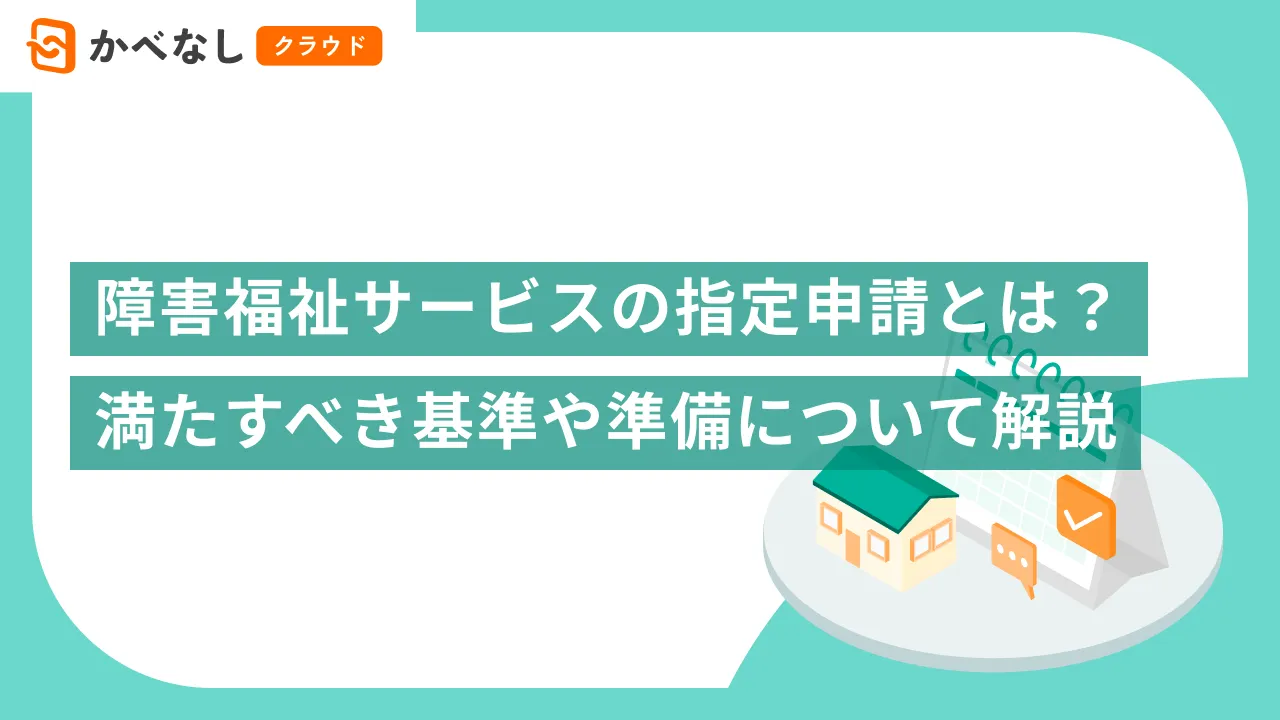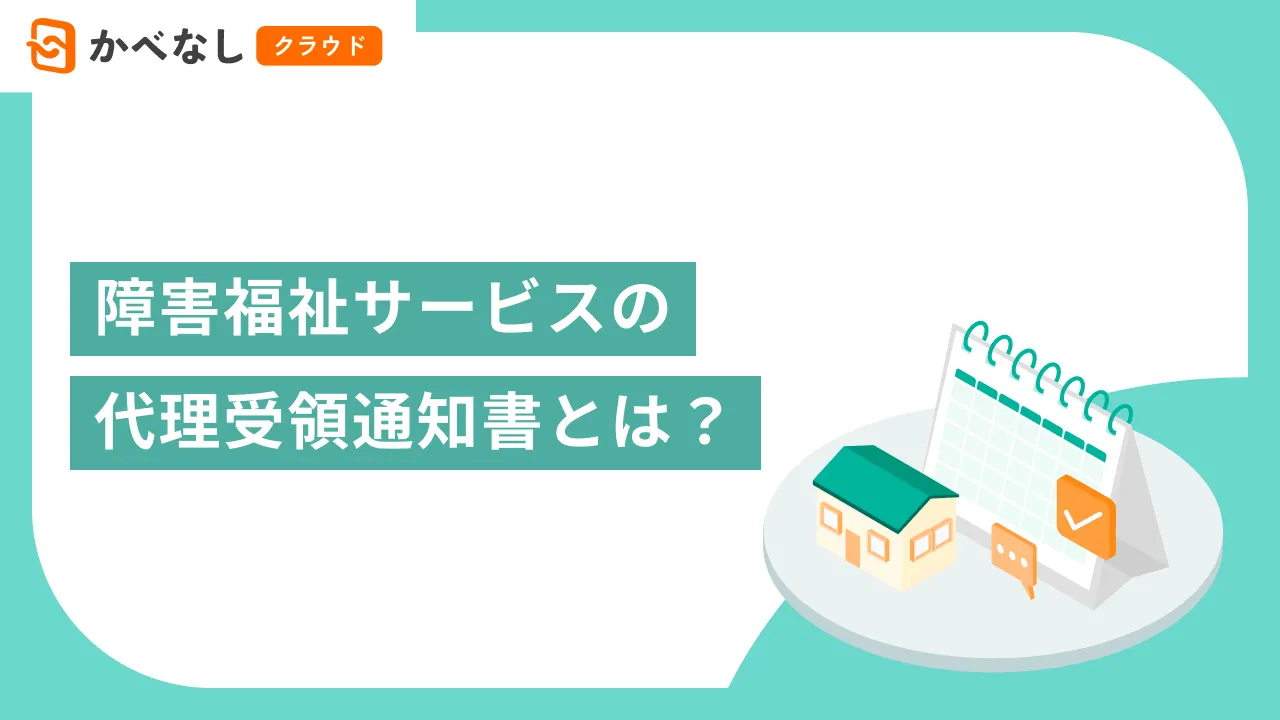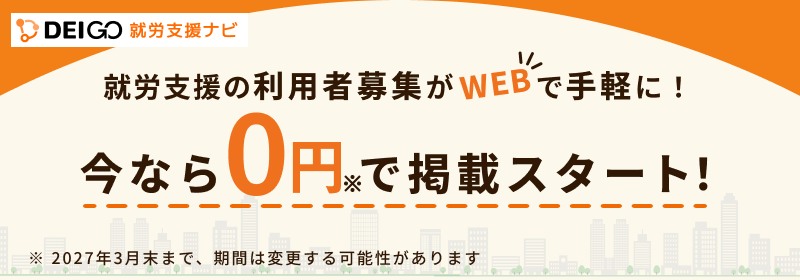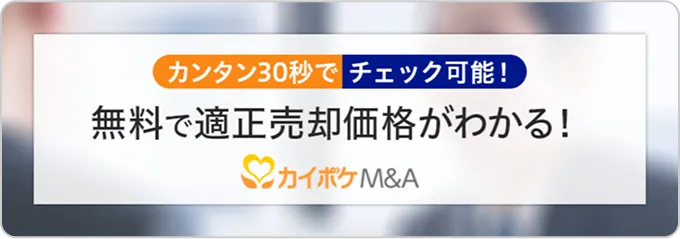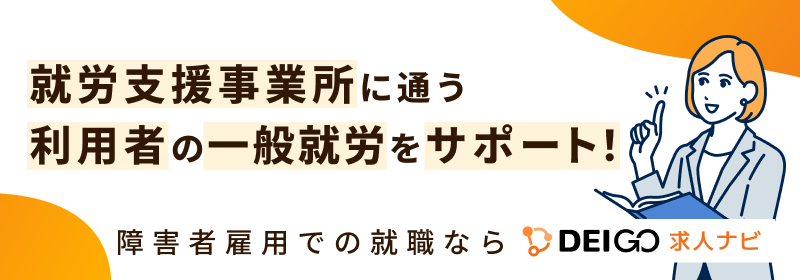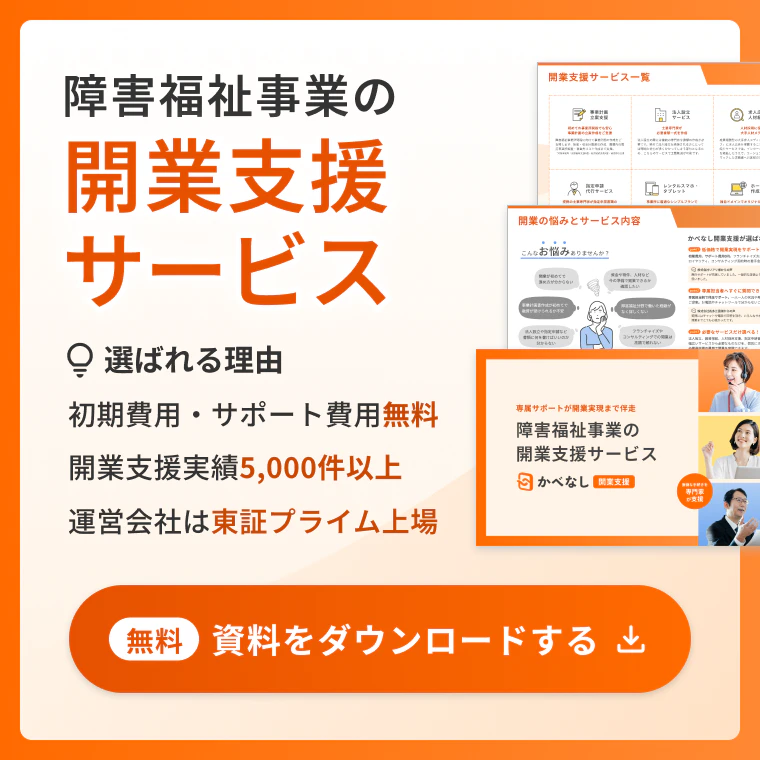障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
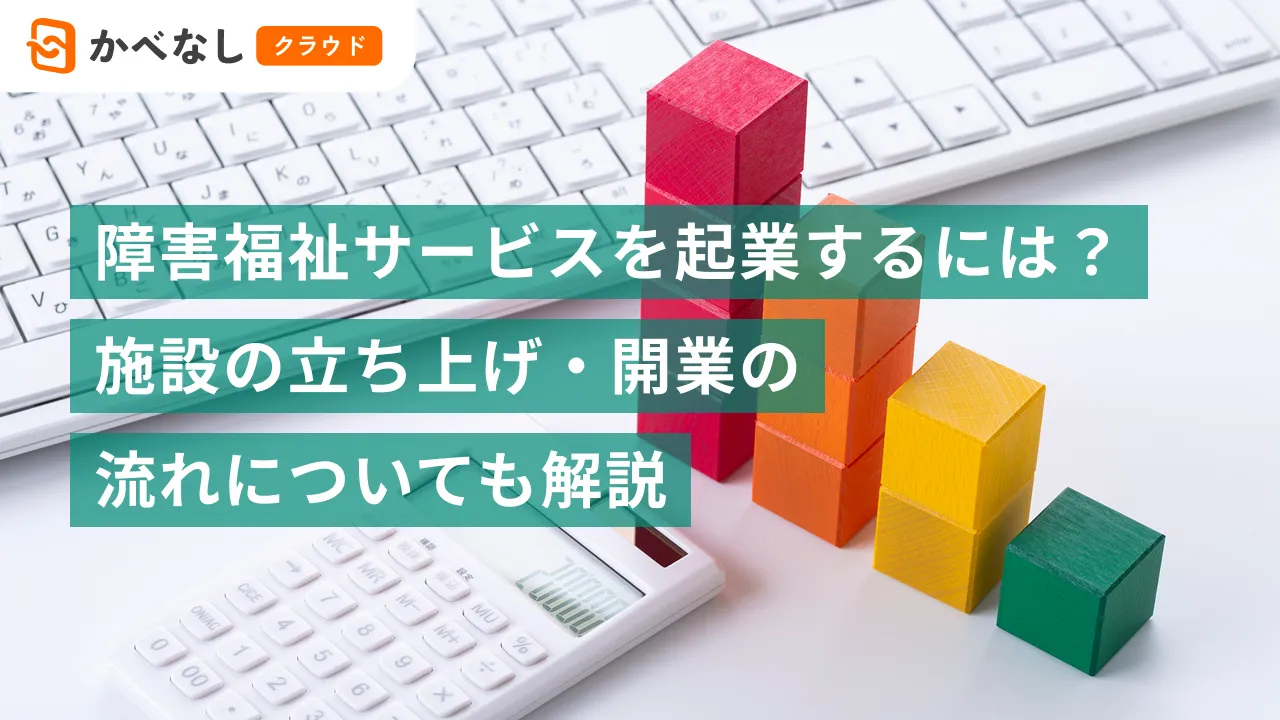
障害福祉サービスの起業・立ち上げを検討している皆様の中には、「障害福祉サービスを起業するにはどうすればいいの?」や「立ち上げ・開業のための条件や基準、必要な資格は何?」などといったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、障害福祉サービスを起業するまでの流れや、立ち上げ・開業に必要な資格、障害福祉サービスの市場の動向などについてご紹介していきます。
障害福祉事業とは?
障害福祉事業とは、主に身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある方の日常生活や社会生活をサポートし、地域の一員としてともに生きることができる社会づくりを目指す事業です。
障害福祉事業は、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスと、「児童福祉法」に基づく障害児支援サービスに分かれています。
「障害者総合支援法」は18歳以上の方を対象にしている一方で、「児童福祉法」は18歳未満の児童を対象としています。
障害福祉サービスの種類
「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスのサービス内容は以下です。
| サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅で排せつ・入浴・食事の介護などを行う |
| 重度訪問介護 | 重度の障害があり、常に介護が必要な方の自宅や外出先で介護を行う |
| 同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難がある方が外出するときに必要な介護を行う |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている方が外出する時などに必要な支援を行う |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が高い方に居宅介護など複数のサービスを包括的に行う |
| 短期入所 | 短期間、夜間も含めた施設で排せつ・入浴・食事の介護などを行う |
| 療養介護 | 医療的ケアと常時介護を必要とする方に看護や介護を行う |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、排せつ・入浴・食事の介護や創作的活動の提供を行う |
| 施設入所支援 | 施設に入所する方に夜間や休日、排せつ・入浴・食事の介護などを行う |
| 自立生活援助 | 定期的な居宅訪問や随時の対応に応じて必要な支援を行う |
| 共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や排せつ・入浴・食事の援助を行う |
| 自立訓練(機能訓練) | 自立した生活が送れるよう一定期間、身体機能の維持・向上のための訓練を行う |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立した生活が送れるよう一定期間、生活能力の維持・向上のための訓練を行う |
| 就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する方に必要な訓練を行う |
| 就労継続支援(A型) | 一般企業での就労が困難な方を雇用し、就労や訓練の機会を提供する |
| 就労継続支援(B型) | 一般企業での就労が困難な方に就労や訓練の機会を提供する |
| 就労定着支援 | 一般就労に移行した方に就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う |
「児童福祉法」に基づく障害福祉サービスのサービス内容は以下です。
| サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 0歳〜6歳の障害のある児童に対して、療育(発達支援サービス)を提供する |
| 放課後等デイサービス | 6歳から18歳までの障害のある児童に対して、放課後や学校休業日に生活に必要な能力の向上のためのサービス等を提供する |
| 保育所等訪問支援 | 保育所や幼稚園など集団生活を営む施設等へ支援員が訪問し、障害児の保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行う |
また、主に障害福祉サービスの利用にまつわる相談に応じる「相談支援」という事業も存在します。
計画相談支援
計画相談支援では、障害のある方が普段の生活を送る中で直面した不安や困りごとへの相談、また、相談者にマッチする障害福祉サービスに関する助言などを行います。
障害児相談支援
障害児相談支援とは、障害児が児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、サービス開始後、一定期間ごとにモニタリングを行い、サービス事業者との連絡調整などを行う事業です。
障害福祉事業の需要と市場の動向
障害福祉事業を立ち上げようと考えている方の中には、障害福祉事業の需要や市場の動向が気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
障害がある方の数は、2016年から2023年にかけて増加傾向にあります。

障害福祉事業は儲かるの?
厚生労働省の「令和5年度障害福祉サービス等経営実態調査」によると、令和4年度の障害福祉事業の全サービス平均の収支差率(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金を含む)の全国平均は「5.6%」です。
収支差率とは、事業全体の利益が収益(売上)に対してどれくらいなのかを表す指標です。
収支差率がマイナスの場合は赤字経営だったことを、収支差率がプラスの場合は黒字経営だったことを意味します。
障害福祉サービス別の平均収支差率の推移は以下の表の通りです。
| サービス名 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 5.3% | 8.5% | 8.3% | 7.0% |
| 重度訪問介護 | 5.9% | 6.9% | 5.6% | 7.2% |
| 同行援護 | 5.1% | 8.7% | 6.2% | 5.9% |
| 行動援護 | 4.0% | 7.5% | 7.4% | 9.0% |
| 療養介護 | 1.6% | 3.6% | 3.5% | 1.6% |
| 生活介護 | 8.9% | 8.3% | 8.3% | 8.5% |
| 短期入所 | 4.0% | 1.4% | 3.2% | 5.9% |
| 施設入所支援 | 6.3% | 2.8% | 4.7% | 7.4% |
| 自立訓練(機能訓練) | 1.3% | -1.2% | 1.2% | 3.2% |
| 自立訓練(生活訓練) | 6.4% | 4.1% | 2.4% | 1.6% |
| 就労移行支援 | 5.5% | 6.8% | 3.2% | 8.4% |
| 就労継続支援A型 | 4.2% | 6.2% | 7.1% | 3.9% |
| 就労継続支援B型 | 6.0% | 4.5% | 4.7% | 5.8% |
| 就労定着支援 | 2.9% | 2.4% | 2.9% | 9.7% |
| 自立生活援助 | 8.0% | 1.7% | -0.8% | 2.7% |
| 共同生活援助 | 8.6% | 5.5% | 6.7% | 5.7% |
(出典:厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」より作成)
ほとんどのサービスで平均の収支差率が0%を超えていることからも、障害福祉事業は『十分に利益が出る可能性のある事業』と言えるでしょう。
一方で、収支差率が0%を下回る事業所も当然存在するため、安定した事業運営をするためにも、開業前に資金調達計画や損益計画を十分に練り、事業運営の指針となる事業計画書を作成するようにしましょう。
立ち上げ後の資金繰りに有効なファクタリング
立ち上げ後、事業所の資金繰りをサポートするサービスもあります。
ファクタリングサービスは、国保連請求をファクタリング会社が買い取ることで早期に資金化できるサービスです。 つまり、通常であればサービスを提供した月の翌々月に国保連から支払われる報酬を早期に受け取ることができます。
入金のタイミングや手数料はファクタリング会社によって異なるので、導入前には確認が必要です。
カイポケのファクタリングなら、業界最安値水準の手数料率で、最短5営業日でのスピード入金が可能です。
障害福祉事業の収益構造
障害福祉事業では、サービス提供を行った対価として得る「障害福祉サービスの報酬」が主な収入になります。障害福祉サービスの報酬の構造は、
- 基本報酬
- 加算・減算
に分類することができます。
基本報酬に対して加算や減算の項目を加減した金額を算出し、負担割合に応じてサービス利用者の方と国保連(国民健康保険団体連合会)に対して請求を行うことになります。
「1.基本報酬」については、障害福祉サービスごとにベースとなる報酬体系が異なります。
例えば、就労継続支援B型における報酬体系は以下のいずれかを選択することができます。
- 「平均工賃月額」に応じた報酬体系
- 「利用者の就労や生産活動への参加等」による一律評価での報酬体系

事業所が属する地域によって1単位ごとに受け取れるお金の単価は決まっており、単位数が増えるほど事業所が受け取れる報酬も多くなるのです。
また、これらの基本報酬とは別で、一定の条件を満たすことで得られる報酬が「加算」、本来満たすべき人員基準や設備基準などを満たさない場合に適用されるのが「減算」になります。
「加算」については、障害福祉サービスごとに様々な種類が存在し、例えば自宅と事業所間の送迎を行った場合に加算される送迎加算や、食事を提供した場合に加算される食事提供体制加算などがあります。
障害福祉事業の開業・立ち上げに必要な条件・資格
障害福祉事業の経営者になるために持っていなければならない資格はありません。
ただし、障害福祉事業を開業・運営していくためには、法人格を有した上で3つの条件を満たしている必要があります。
- 法人格を有している
- 人員基準を満たす
- 設備基準を満たす
- 運営基準を満たす
それぞれ詳しく解説していきます。
条件1:法人格を有している
障害福祉事業は個人事業主では運営することができないため、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得する必要があります。
法人形態については、それぞれにメリット・デメリットがあるので、準備できる資金、開業後に運営する中での意思決定のしやすさや資金調達方法の幅広さなどを踏まえて最適な法人格を選ぶようにしましょう。
例えば、株式会社は合同会社と比べると、社会的な信用も高く、株を発行して資金調達ができる一方で、設立までの手続きが多く、設立にかかる費用も高くなります。
条件2:人員基準を満たす
障害福祉事業の人員基準には、開業・運営する上で必要な職種や配置人数が定められています。
人員基準を満たさないと事業所を開業することはできず、開業後も基準を満たし続ける必要があります。
満たさない場合は報酬の減額や行政指導につながる場合もあるので注意が必要です。
例として、主要な障害福祉サービス別での人員基準に定められている必要な職種をご紹介します。
| サービス種別 | 人員基準に定められる職種 |
|---|---|
| 生活介護 | ・管理者
・サービス管理責任者 ・医師 ・看護職員 ・理学療法士または作業療法士 ・生活支援員 |
| 相談支援 | ・管理者
・相談支援専門員 |
| グループホーム | ・管理者
・サービス管理責任者 ・世話人 ・生活支援員 ・夜間支援従事者 |
| 就労継続支援A型・B型 | ・管理者
・サービス管理責任者 ・職業指導員 ・生活支援員 |
| 就労移行支援 | ・管理者
・サービス管理責任者 ・生活支援員 ・職業指導員 ・就労支援員 |
条件3:設備基準を満たす
障害福祉事業の設備基準には、障害福祉事業を開業・運営するにあたって必要な設備や備品が定められています。
開業前に行う指定申請では、設備・備品などの一覧表や建物の平面図などを通して、設備基準をクリアできているかどうかが審査されることになります。
ここでは例として、生活介護の設備基準に定められている設備や備品をご紹介します。
| 設備名 | 設備基準 |
|---|---|
| 訓練・作業室 | ・訓練や作業に支障がない広さにする
・訓練や作業に必要な機械・器具を備える |
| 相談室 | 室内において話し声が漏れないような工夫をする(仕切りを設けるなど) |
| 洗面所・トイレ | ・サービス利用者の特性に応じたものにする
・洗面所とトイレの兼用は不可 |
| 多目的室 | ・サービス利用者の特性に応じたものにする |
条件4:運営基準を満たす
障害福祉事業を運営するためには、サービスの利用にあたっての留意事項や緊急時における対応方法などの運営規程を定めておく必要があります。
定めなければならない運営規程には以下のようなものがあります。
【事業の運営についての重要事項に関する運営規程】
- 事業の目的や運営の方針
- 従業員の職種や人数、職務の内容
- 営業日や営業時間
- サービス利用者から受領する費用の種類や金額
- サービスの利用にあたっての留意事項
- 緊急時などにおける対応方法
- 非常災害対策
- 事業の対象となる障害の種類
- 虐待防止のための措置
- その他運営に関する重要事項
開業までに対応しなければならない事項も多いため、余裕をもって準備を進めましょう。
障害福祉事業は一人で起業できるの?
人員基準を満たさないと障害福祉サービスを開業することはできないため、障害福祉サービスを一人で起業し、運営することは基本的にはできません。
ただし、相談支援事業などでは管理者と相談支援専門員を兼ねることができるので、一人で起業することも可能です。
起業する障害福祉サービスの種類が決まったら、人員基準や設備基準をよく確認するようにしましょう。
障害福祉事業の開業・立ち上げに必要な資金の調達方法
障害福祉サービスを開業するにあたって資金調達の方法を解説します。
開業時の資金調達方法としては、『自己資金』と『金融機関からの融資』を組み合わせるケースが多いです。
自己資金
自己資金とは、自身が所有・集めた資金等のうち、事業に投資できる資金のことです。
金融機関から融資を受ける際は、開業資金の総額の10分の1から3分の1は自己資金として用意する必要があると言われています。
金融機関からの融資
金融機関からの融資を受ける場合には、金融機関のホームページ等から融資制度についての情報を集めて、必要な書類を作成し、相談の電話をかけます。
【融資を受けるために必要な書類の例】
- (新規法人設立以外の場合)決算書3期分
- 事業計画書
- 資金計画書(資金繰り表)
- 事業所のパンフレット
日本政策金融公庫の融資制度
障害福祉サービスの開業時には、政府系金融機関である「日本政策金融公庫」が、多くの方から選ばれています。
日本政策金融公庫は、創業時の企業に積極的に融資するための融資制度があるので、融資の条件等を比較する上でも候補のひとつとして考えておくのが良いでしょう。
| 融資制度の種類 | 概要 |
|---|---|
| ソーシャルビジネス支援資金 | 障害福祉や保育など社会的課題の解決を目的とするサービス事業向けの融資制度 |
| 新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連) | 新たに事業を始める事業主等で女性または35歳未満か55歳以上の方が利用できる融資制度 |
障害福祉事業の開業・立ち上げの流れ
障害福祉事業の開業は以下のようなステップで進めます。
【障害福祉事業の開業までのステップ】
- 事業計画書の作成
- 法人設立
- 開業のための資金の調達
- 物件探し・契約
- 従業員の採用
- 物件のリフォーム
- 備品の調達
- 指定申請
- 請求ソフトの手配
- 利用者様の獲得
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:事業計画書の作成
事業計画書には、どのような事業を行うのかを示した事業方針や、競合となる事業所に関する情報、収支の見通しなどを記していきます。
事業計画書は、主に指定申請や金融機関から資金を借り入れる際に使用される書類です。
計画の内容が非現実的な場合は、指定申請で開業を認められない可能性や金融機関から融資を受けられない可能性などがあります。
経営者としても、この事業計画を踏まえて事業を運営していくことになるので、できる限り綿密な計画を作成するようにしましょう。
事業計画書の作成方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ステップ2:法人設立
まず、会社の目的や役員、株主などを決めます。その上で、役員の同意書や定款などの登記に必要な書類を作成していきます。
書類の準備ができたら、書類を管轄の法務局へ提出し、法務局の審査を受けます。無事に審査を通過し、登記に必要な税金を納付できたら手続きは完了です。
税金については、例えば株式会社を設立する場合だと、印紙税や登録免許税などを合わせて20万円前後の費用が発生します。
また、登記手続きにおいては書類の不備がある度に、修正して書類を再提出する必要があります。
何度も法務局に行く時間を確保できない方は、行政書士などの専門家のサポートを受けるとよりスムーズに手続きを進めることができます。
ステップ3:開業のための資金の調達
障害福祉事業の開業には、一般的に法人設立費、物件準備にかかる費用、内装施工費、人件費などで、一般的に『1,000万円』ほどの資金が必要になります。
一方で、そのすべてを自分の貯蓄だけでカバーできる人は少ないでしょう。
開業に必要な資金を自分の貯蓄だけで準備できない場合は、金融機関などから借り入れを受けるケースが多いです。
障害福祉事業の資金調達方法について、 詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ステップ4:物件探し・契約
障害福祉事業では、事務室や相談室など設備基準を満たすことができる物件を探す必要があります。
また、設備基準以外にも、現実的に支払い可能な賃料の条件や、サービスを利用する方々がアクセスしやすい立地の条件などを踏まえて物件を探していきます。
物件を探す方法として、インターネットや開業予定地域の不動産会社への相談なども行い、幅広く情報を集めましょう。
ステップ5:従業員の採用
障害福祉事業として「指定」を受けるためには、人員基準を満たさなければなりません。
そのため、ステップ8にて解説する指定申請を行う前の段階で、求人を行い、従業員を採用しておく必要があります。
障害福祉事業で必要な従業員数は、どれほどのサービス利用者数を見込んでいるかによっても変動するので、事業計画を踏まえて採用人数の目安を決めていきます。
採用方法としては、ハローワークや求人雑誌のほかに、インターネットの求人広告や人材紹介などが存在します。採用に使える費用も踏まえながら採用方法を決めるようにしましょう。
ステップ6:物件のリフォーム
障害福祉事業の「設備基準」を満たすために、訓練・作業室や相談室間の仕切りの設置、洗面所やトイレの増設など、必要に応じて物件をリフォームする必要があります。
また、「設備基準」を満たすことができていても、サービスを利用する方にとってより居心地のよい環境になるように、壁紙の張替えなどのリフォームの実施も想定しておく必要があります。
ステップ7:備品の調達
障害福祉事業所で働く従業員が使用するものとして、電話やFAX、オフィスデスクやオフィスチェア、パソコンやタブレットなどの通信機器といった備品が必要です。
また、サービスを利用する方々が使用するものとして、作業用具や机、いす、ティッシュやトイレットペーパーなどの消耗品の準備も必要です。
納品に時間がかかる場合もあるので、計画的に準備を進めていきましょう。
ステップ8:指定申請
障害福祉事業を開業するためには、「指定申請」という手続きを行い、管轄の自治体より許認可を得る必要があります。
指定申請手続きでは、各自治体によって定められている必要書類を準備・提出します。
申請書類が受理されてから指定され、開業が可能になるまでの期間は指定権者によって違いはありますが、おおむね1~2か月程度を要します。
また、指定申請の前段階として「事前相談」が必要となるケースもあるので、開業を希望する月の『3か月前〜6か月前』までには一度、管轄の自治体の担当窓口へ相談するようにしましょう。
障害福祉サービスの指定申請に必要な書類の一覧
障害福祉事業を開業する際に必要な書類の例をご紹介します。
【障害福祉事業の指定申請書類の例】
- 指定協議事前調査シート
- 事業計画書
- 支援方法・組織体制の内容
- 収支予算書
- 運営規定
- 事業所一覧
- 社会福祉施設等における耐震化状況調査票
- 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票
- 法人登記簿謄本
- 誓約書
自治体によって必要な書類が異なる場合もあるので、詳しくは管轄の自治体の窓口やホームページで確認するようにしましょう。
ステップ9:業務支援システムの手配
障害福祉事業では、サービス提供の対価を得るために、国保連とサービスを利用した方々へ請求する必要があります。
請求業務をスムーズに行うためにも、サービスを利用する方々への支援記録の管理ができる業務支援ソフトの導入を検討しましょう。
業務支援ソフトの機能としては、支援記録の作成や個別支援計画の管理、利用者への交付書類の管理などが中心で、ほかにも様々な機能があります。
料金や機能の種類はソフトによって異なるため、複数のソフトを比較しながら導入するソフトを決めていきましょう。
ステップ10:サービス利用者の獲得
開業する日が決まったら、開業日に向けて、事業所紹介用のパンフレットや名刺、ホームページなどを作成し、サービスを利用する方々の獲得を目的にした集客を開始しましょう。
集客方法としては、病院や地域の保健所、保健センターなどの関係機関への営業活動やSNSを活用した情報発信、WEB広告などが考えられます。
予算も踏まえながら、可能な範囲で集客活動を実施していきましょう。
障害福祉事業の開業を「かべなし開業支援」がお手伝いします!
障害福祉事業の開業には、半年から1年ほどの準備期間が必要です。
『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。
「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集だけでは抜け漏れがありそうで不安だ」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度『かべなし開業支援』の資料をご請求ください。
まとめ
ここまで、障害福祉事業を開業するまでの流れや、立ち上げに必要な資格、障害福祉事業の市場動向などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
障害福祉事業を開業するためには、物件探しから資金調達、従業員の採用までやることがたくさんあり、時間もかかります。
まずは開業に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。
かべなし開業支援では開業までのスケジュール作成のお手伝いも行っておりますので、ぜひお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
開業に関する資料をダウンロード
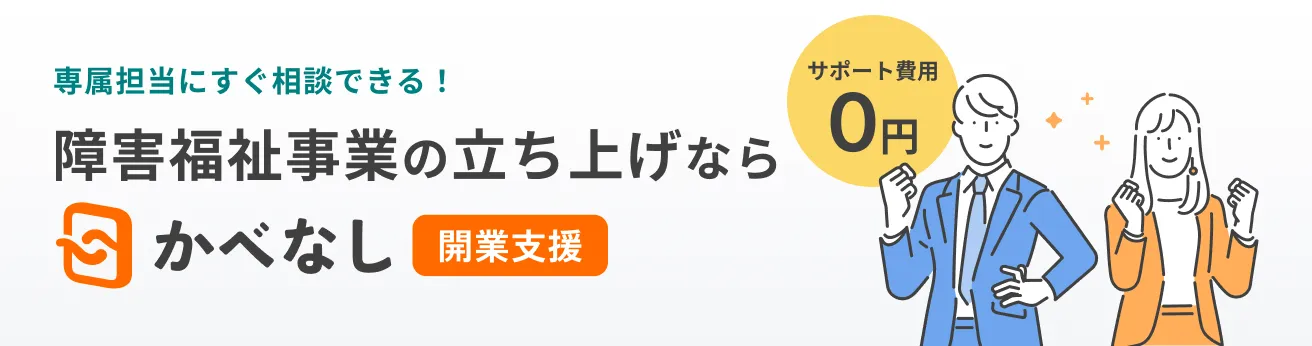

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。