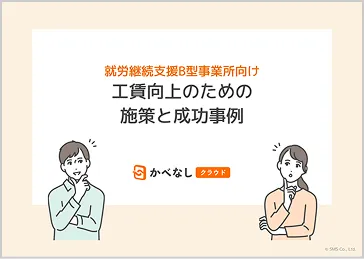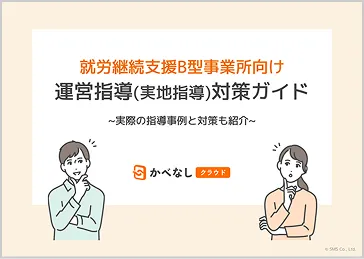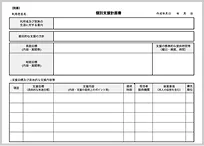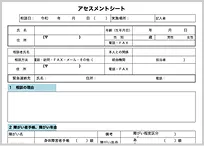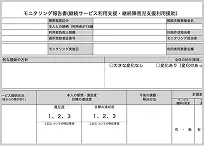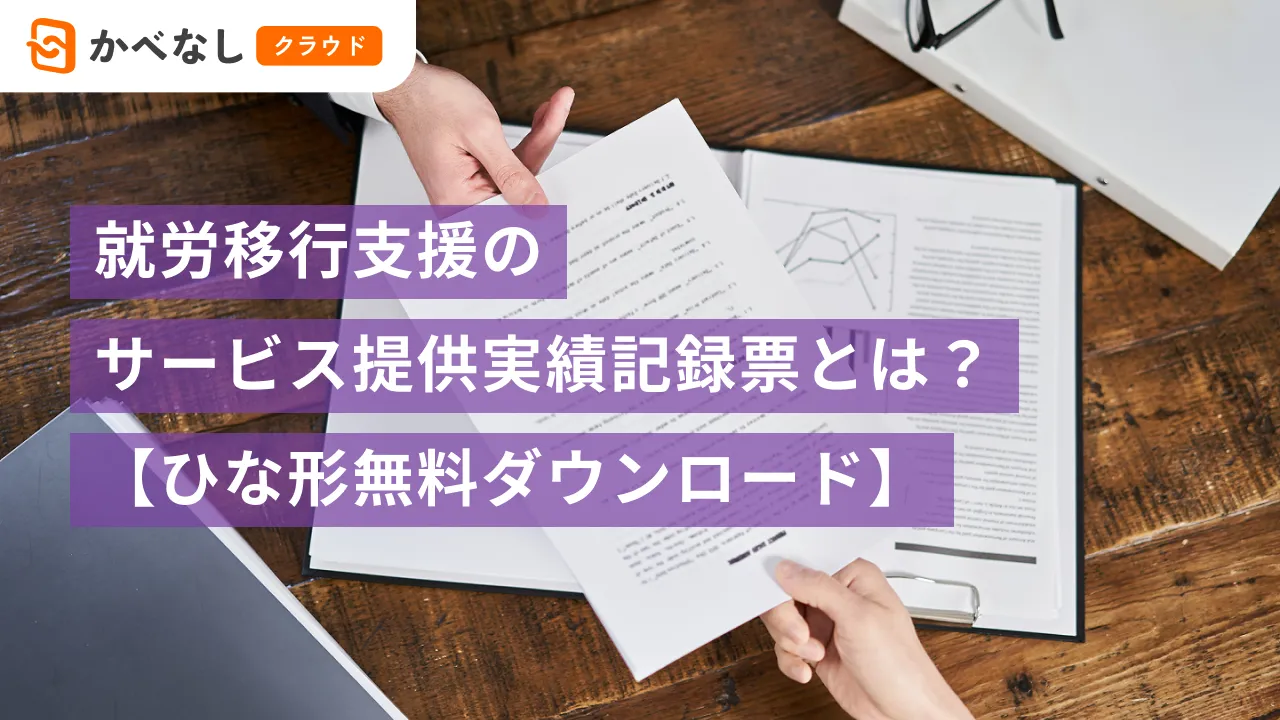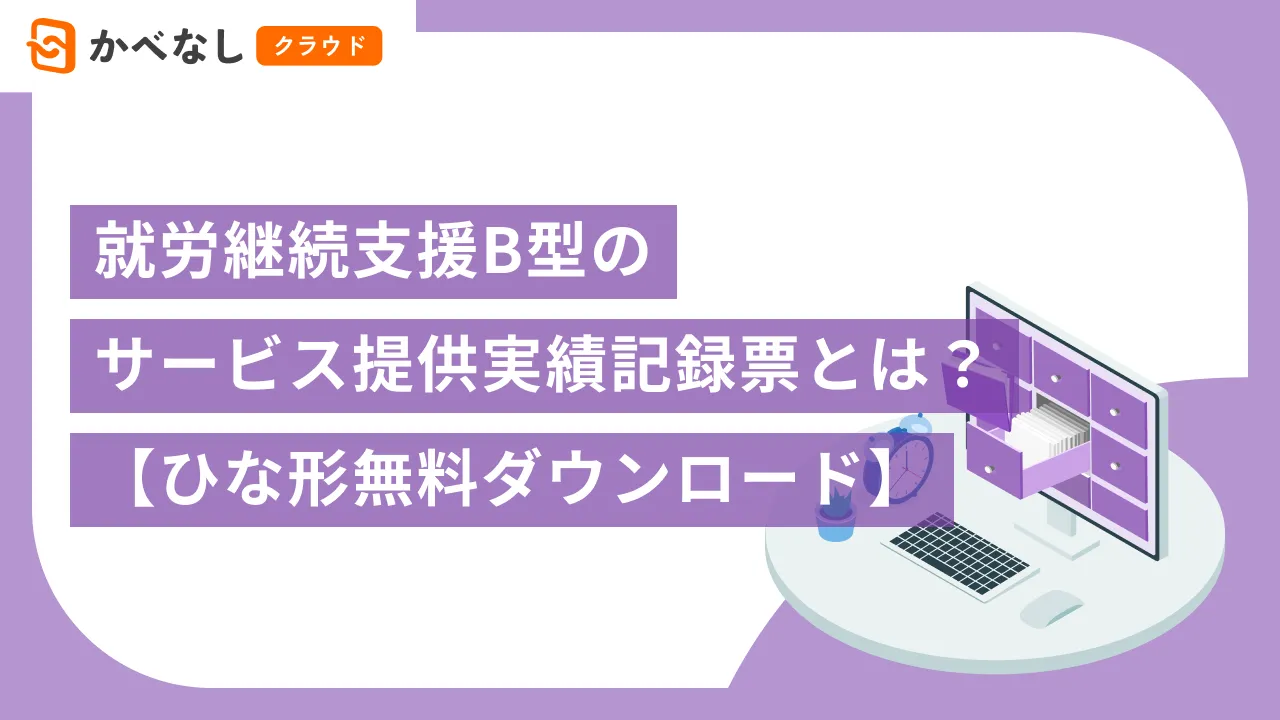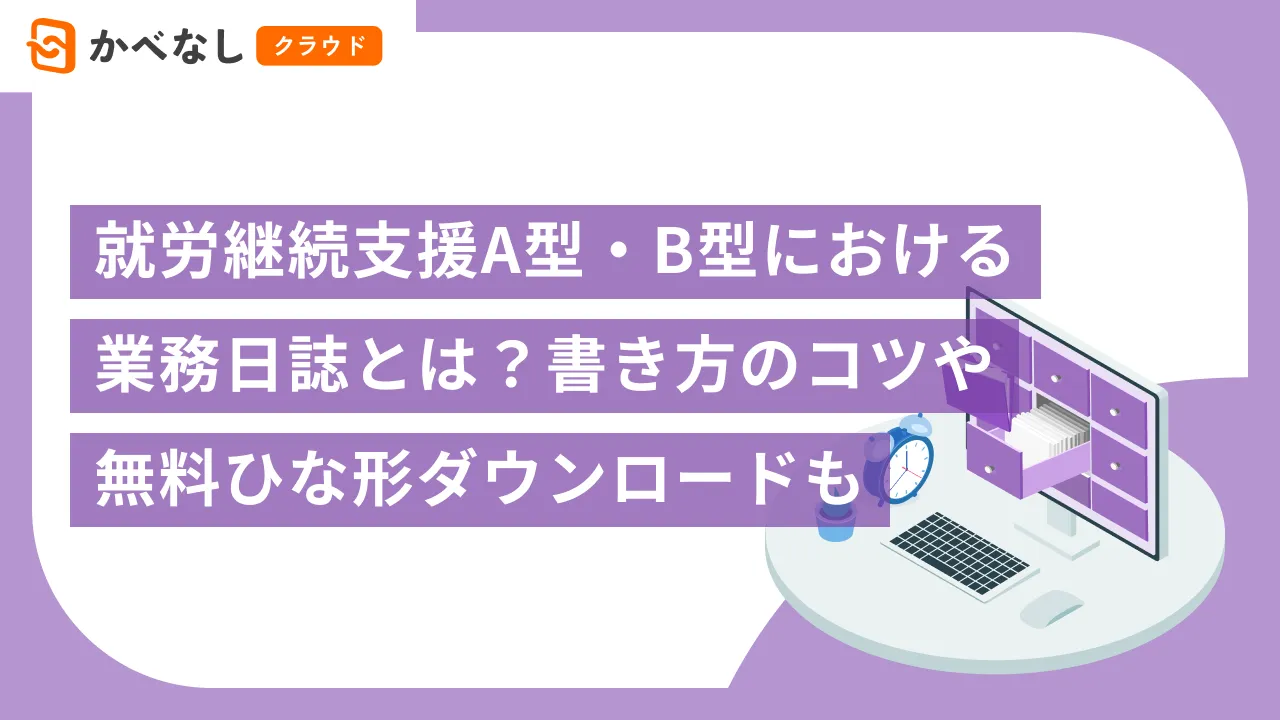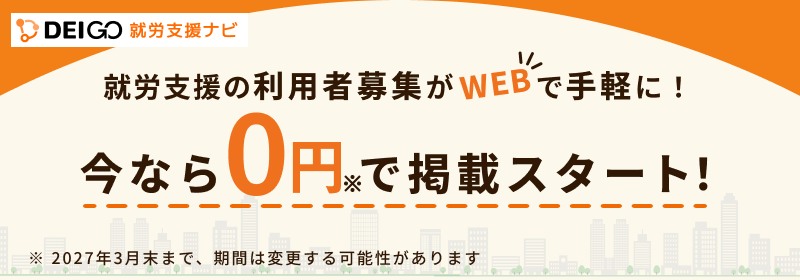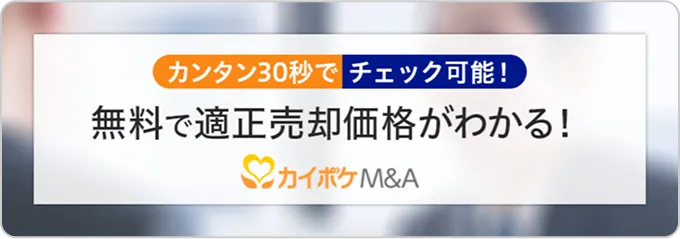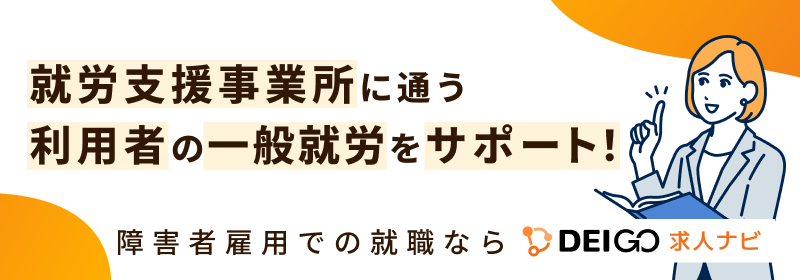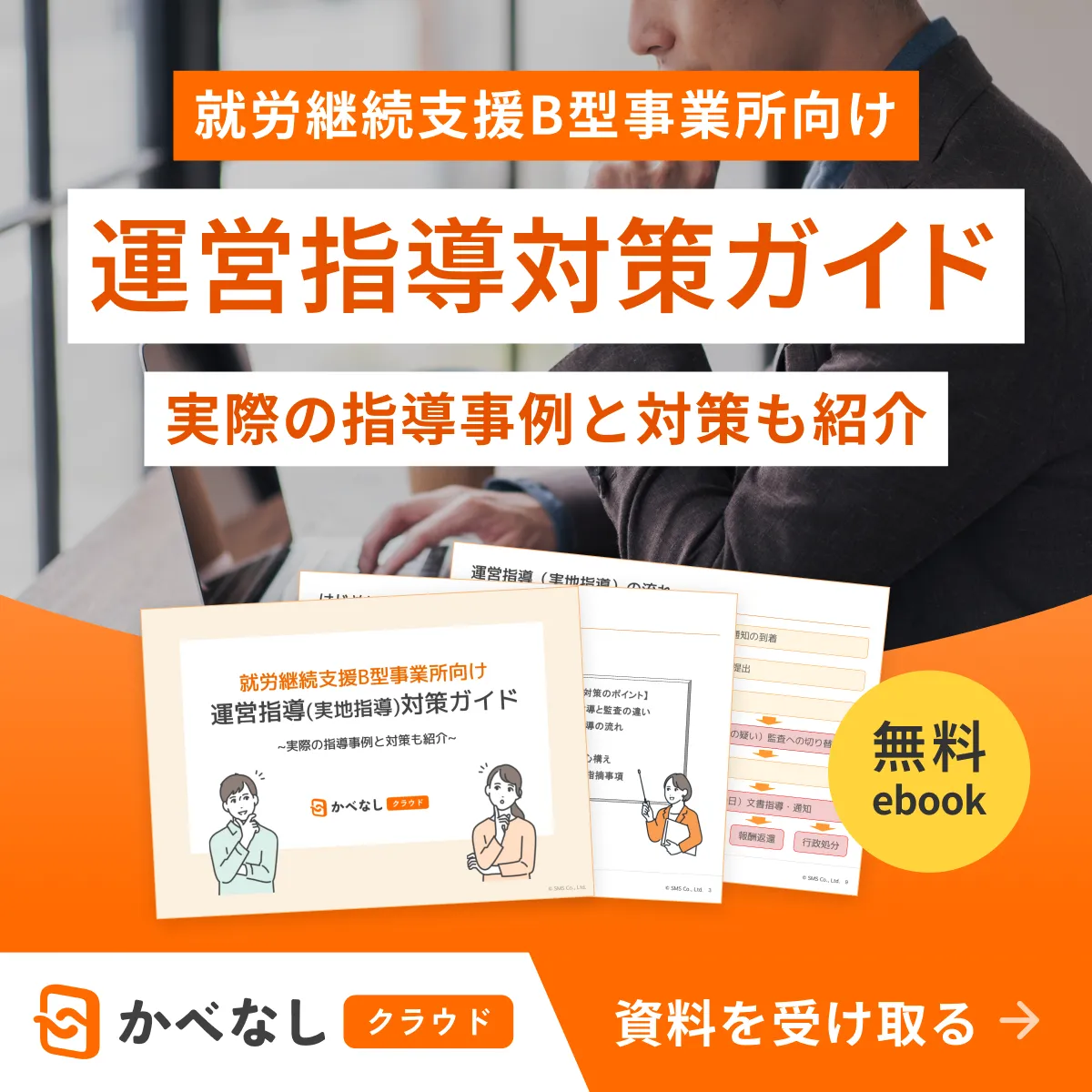障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
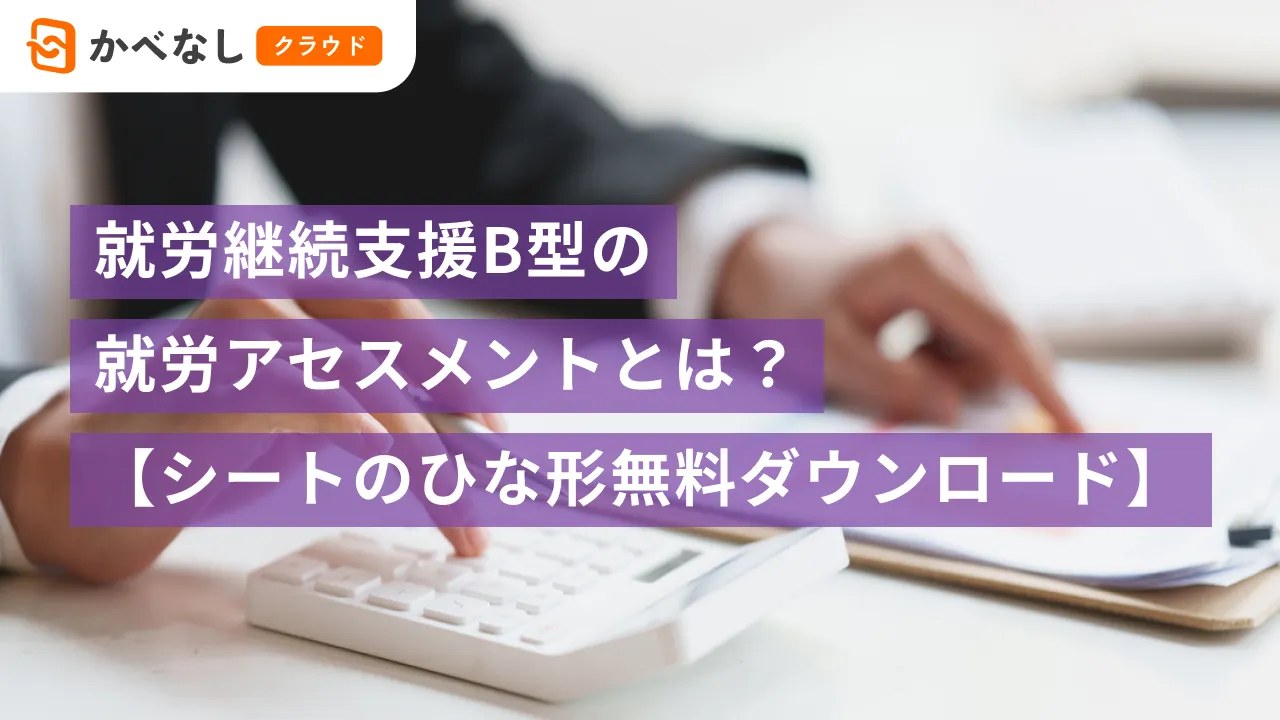
就労継続支援B型で働かれている方々の中には、就労アセスメントのやり方や目的がわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では就労継続支援B型の就労アセスメントについて、その目的や実施の流れについて解説します。
就労継続支援B型におけるアセスメントとは?
就労継続支援B型などの就労系サービスでは、主に個別支援計画等の作成で活用するアセスメントと、利用者の働くための能力把握を行う「就労アセスメント」が実施されます。
そもそもアセスメントとは?
障害福祉分野でよく行われるアセスメントとは、事業所が利用者に合った支援を提供するために、面談や観察などを行って利用者の状態を把握し、課題の分析を行うことです。利用者の心身の状況や周辺環境、利用者が生活する上でどのような課題をもっているのかなどを、対面でのヒアリングを通して把握していきます。
利用者の「今」の状態と、支援を受けた先にある「なりたい姿」を把握し、その情報に基づいた支援計画を立てることで、利用者の希望に合った支援を実現することを目的としています。そのため、利用者が抱える課題の解決に向け、効果的な支援を行うことを念頭においてヒアリングする必要があります。
就労アセスメントとは?
「就労アセスメント」は主に就労系サービスで実施される手法で、利用者が就労を行う上で必要な力や課題を把握し、支援に活用するために行うアセスメントです。
通常のアセスメントが生活全体の支援を主眼においているのに対し、就労アセスメントはより働く力に焦点を当てており、就労の準備や定着に活かすことを目的としています。
就労継続支援B型のアセスメント実施のタイミング
利用者の状況を把握するアセスメントは、利用者との初回面談時に行うのが一般的です。その他、支援をする中で利用者の状況に変化が生じた際にも再アセスメントを行う場合があります。
就労継続支援B型のアセスメントシートとは
アセスメントシートとは?
アセスメントシートは、アセスメントを行った際に取得した利用者の課題やニーズを記載し、情報の集約や分析のために使用する書類です。
個別支援計画の基礎資料として活用されるほか、支援に係る職員間で共有することで利用者の状況を的確に把握し、共通認識をもつことで質の高い支援を提供するためにも役立ちます。
アセスメントシートに盛り込む項目
アセスメントシートには、一般的に以下のような内容を記載します。
- 氏名、生年月日、住所などの基本情報
- 障害に関する情報
- 家族の状況
- 福祉サービス等の利用状況
- 医療に関する状況
- 社会参加等について
- 日中の活動について
- 生活環境について
- 利用者本人の希望 など
就労継続支援B型のフェイスシートとは
アセスメントシートと似た書類として、フェイスシートがあります。フェイスシートは利用者の基本情報を整理して記録し、職員間で共通の理解をもつために使用される資料です。
また、緊急時の対応資料としても活用されるもので、活用シーンや活用のされ方がアセスメントシートと異なります。
<フェイスシートの項目例>
- 氏名、生年月日、家族構成などの基本情報
- 障害種別や手帳の有無
- 医療関連の情報
- 緊急連絡先
- 支援上の留意点 など
就労継続支援B型の就労アセスメントの流れ
就労継続支援B型を利用する際の就労アセスメントの流れは以下の通りです。
- アセスメントの計画・準備
- 情報収集
- 個別面談と振り返り
- 結果の統合と評価
1.アセスメントの計画・準備
利用者本人やその家族、支援員が面談を行います。そこでアセスメントの目的等について確認し、認識合わせを行います。
ここで利用者のこれまでの職歴や得意・苦手などをヒアリングし、アセスメントの方向性を定めます。
2.アセスメント実施
コミュニケーションや生活リズム、体調など、利用者の様々な情報を取得し、記録していきます。実際の作業や模擬作業を行い、そこからできることや苦手なことを判断することもあります。
3.個別面談と振り返り
定期的に利用者と面談を行い、アセスメントで得られた情報を共有することで、利用者自身の自己評価に繋げます。こうすることで、自身の理解をより深めてもらいます。また、支援員からのフィードバックを踏まえた強みや課題もここで共有します。
4.結果の統合と評価
取得した情報をもとに、利用者1人ひとりの就労に関する能力や特性を評価します。得意な作業・苦手な作業・支援があればできることなど、利用者に適した環境をまとめます。
就労継続支援B型の就労アセスメントの注意点
- 就労アセスメントでは、「評価・見極め」ではなく利用者本人の意向を踏まえ、将来を一緒に考えるスタンスで臨みましょう。
- 課題だけでなく、得意な状況・環境も明確にすることで、強みと課題をバランスよく捉えましょう。
- 就労アセスメントでも、生活全般の課題は考慮できるようにしましょう。
- どんな作業が可能か、どの程度支援が必要なのかを明確に記載しましょう。
就労選択支援開始後の就労アセスメント
令和7年10月から、新たに就労選択支援が始まります。それに伴って就労継続支援B型は一部、サービス利用の手順が変更されます。
就労継続支援B型の利用要件として、「就労選択支援でアセスメントを受けていて就労に関わる課題などの把握ができている」が就労継続支援B型の要件に加わることになりました。
そのため就労継続支援B型の利用を検討されている方は、その前に就労選択支援を利用する必要があります。
ただし、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、サービスを受けるまでに待機時間が発生してしまう場合には、就労移行支援事業所による就労アセスメントを受けることで就労継続支援B型を利用することが可能です。
就労選択支援についてはこちらの記事をお読みください。
就労継続支援B型の記録・請求ソフトなら「かべなしクラウド」
『かべなしクラウド』は、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンから日々の記録を手軽に登録し、利用者ごとに情報を一元管理することができます。
また、電子サイン付タイムカードや個別支援計画・サービス等利用計画の予定管理機能などもすべて1つのソフトで完結するため、記録や帳票作成の業務時間を大幅に短縮することができます。
利用料金は月額9,800円~(税抜)。
「少しでも業務効率を改善したい」と考えている方は、ぜひ一度『かべなしクラウド』の資料をご請求ください。
まとめ
ここまで、就労継続支援B型の就労アセスメントについて解説してきました。
通常のアセスメントとはやや役割が異なる就労アセスメントですが、利用者本人の希望に寄り添い、その希望にあった支援を行うために利用するという意味では共通しているため、その視点を持ちながら取り組むのが理想的です。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
ソフトに関する資料を
ダウンロード


事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。