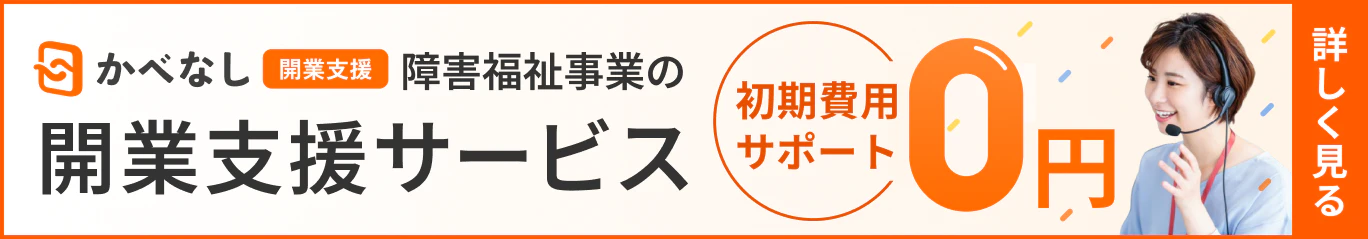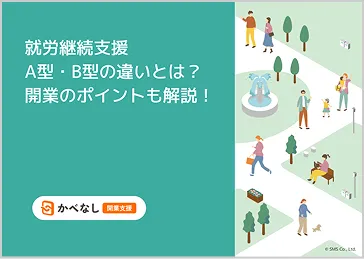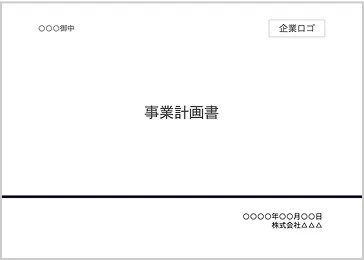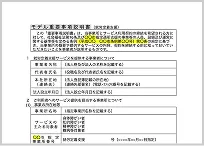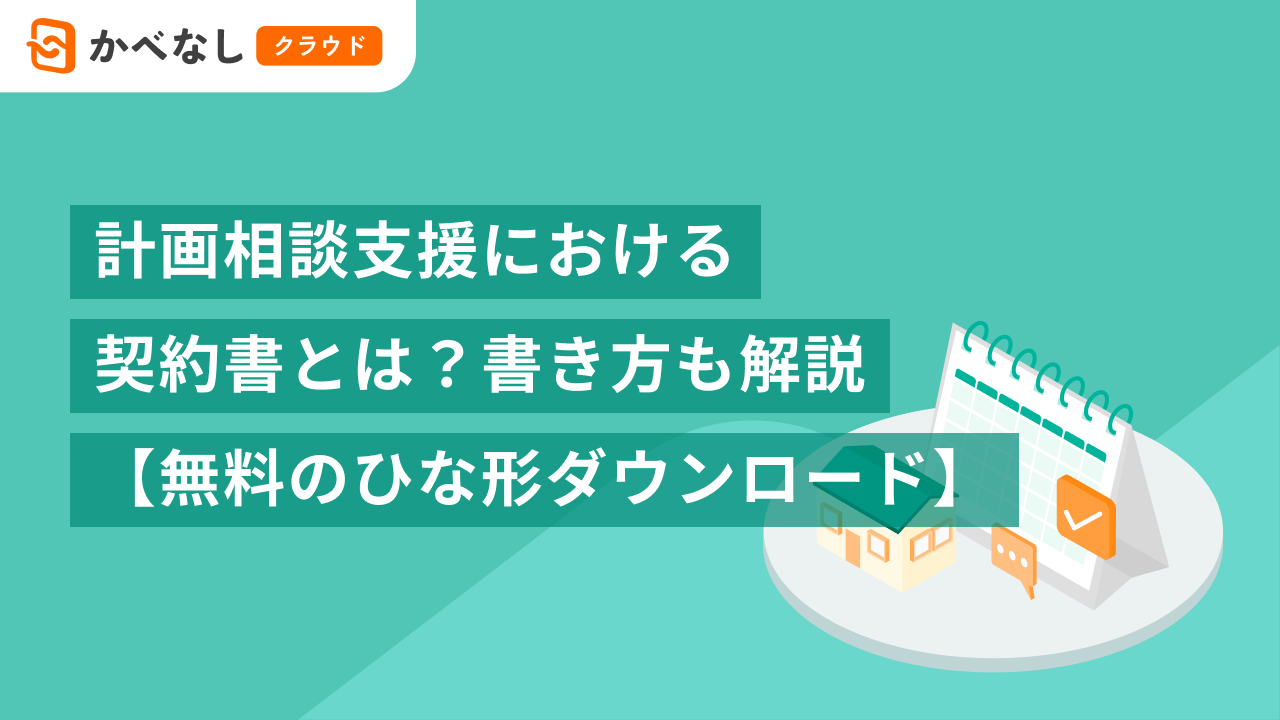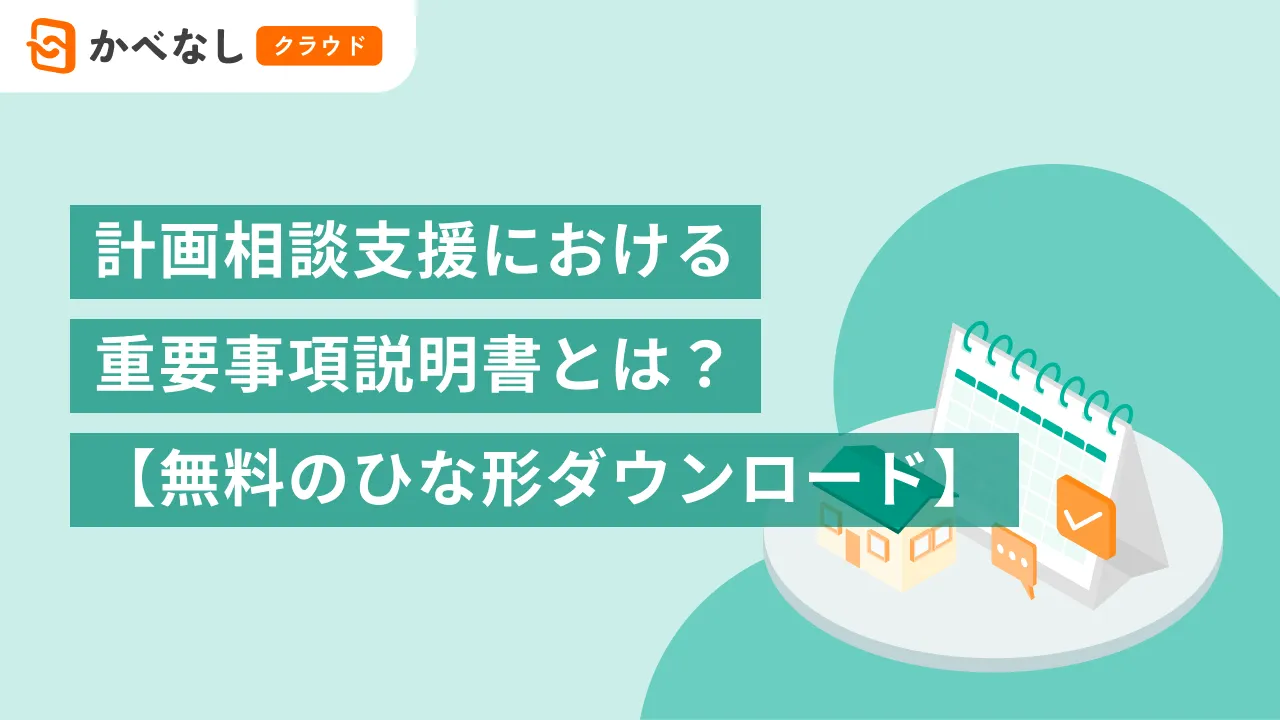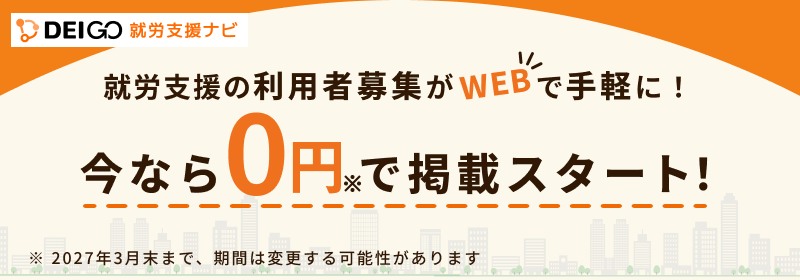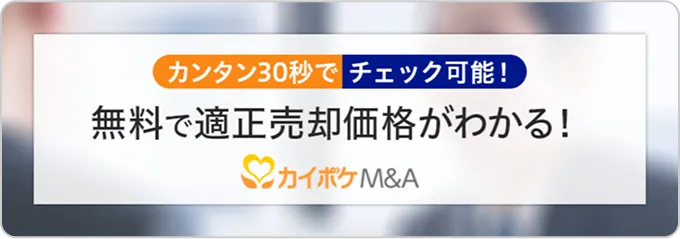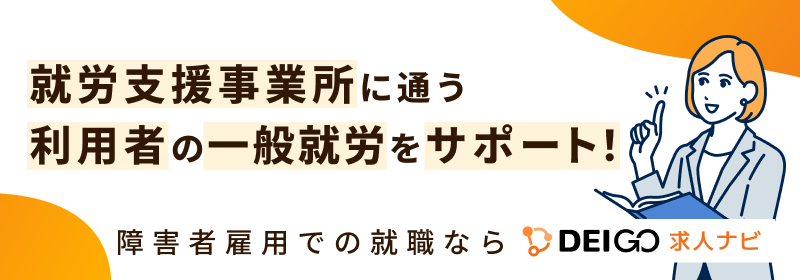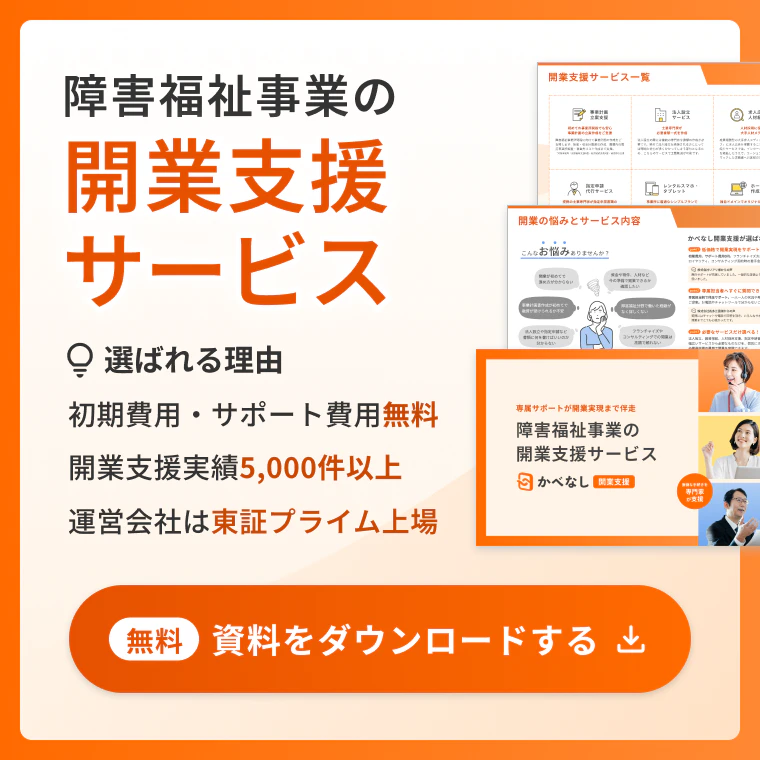障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
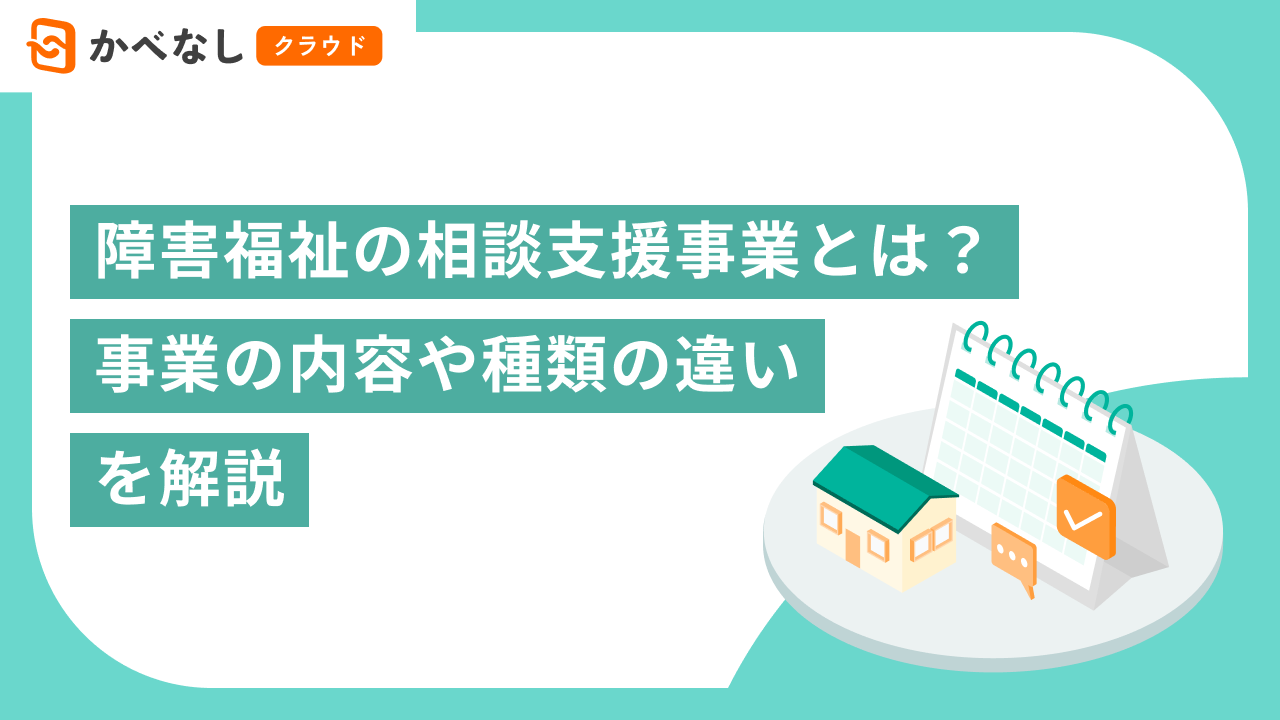
相談支援事業には、複数の種類がありそれによって事業所も2種類に分けられます。
この記事では、相談支援事業を各種類ごとに比較し、事業所と事業の関係についても解説していきます。
相談支援事業とは
「相談支援事業」は、障害のある方々が地域で自立した生活を送るために欠かせない、福祉サービスの利用をサポートする重要な役割を担っています。
相談支援事業所の種類と提供サービスの関係
相談支援事業所は、提供する相談支援事業の種類によって、以下の3つに分けられています。
- 特定相談支援事業所
- 一般相談支援事業所
- 障がい児相談支援事業所
事業所の種類を理解することは、どの事業所がどのサービス(計画相談支援や地域移行支援など)を提供できるのかを把握する上で非常に重要です。
特定相談支援事業所とは
特定相談支援事業所は、主に成人(18歳以上)の障がいのある方が利用する障害福祉サービスに関する支援を行う事業所です。
提供しているサービスは下記の2種類で、それぞれ対象者が異なります。
| 提供サービス | 対象者 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 基本相談支援 | すべての障がいのある方 | 地域生活支援事業 |
| 計画相談支援 | 障害福祉サービス利用者・利用を希望する方 | 障害者総合支援法 |
相談支援では障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、施設入所支援など)の利用に必要な「サービス等利用計画」の作成と、利用開始後のモニタリング(継続サービス利用支援)を行います。
開業するためには、法人格を取得し市町村から「特定相談支援事業者」として指定を受ける必要があります。
一般相談支援事業所とは
一般相談支援事業所は、地域移行や地域定着を専門的に支援する事業所です。
こちらもサービスは下記の2種類で、それぞれ対象者が異なります。
| 提供サービス | 対象者 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 基本相談支援 | すべての障がいのある方 | 地域生活支援事業 |
| 地域相談支援 | 地域生活への移行・定着を希望する方 | 障害者総合支援法 |
施設や精神科病院に入院している方が退院・退所後に地域移行・定着を希望される場合に、地域で生活を始めるための「地域移行支援」や、地域生活を継続するための緊急時対応を含む「地域定着支援」を提供します。
開業するためには、法人格を有して都道府県や指定都市、中核市のいずれかから「一般相談支援事業所」として指定を受ける必要があります。
障害児相談支援事業所とは
障害児相談支援事業所は、主に障害のある18歳未満の方が利用する障害児通所支援に関する計画作成を担う事業所です。
| 提供サービス | 対象者 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 障害児相談支援 | 障がい児通所支援利用者・利用を検討している方 | 児童福祉法 |
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援の利用に必要な「障がい児支援利用計画」を作成し、利用開始後のモニタリングを行っています。
開業には、市町村から「障害児相談支援事業者」として指定を受ける必要があります。
相談支援事業の種類と全体像
この事業は、大きく4つの支援内容に分けられ、利用者の年齢や生活状況に応じて提供されます。
相談支援事業比較表
相談支援事業の種類を比較しやすいように表にまとめました。
根拠となる法律や対象者の他、事業者向けに平均的な収支差率(障害福祉サービスの収入額 - 障害福祉サービスの支出額)/ 障害福祉サービスの収入額)についても記載しています。
| 種類 | 根拠法/実施主体 | 対象者 | 目的と役割 | 収支差率 |
|---|---|---|---|---|
| 基本相談支援 | 地域生活支援事業
(市町村実施) |
すべての障がいのある方やその保護者 | 障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行う | - |
| 地域相談支援 | 障害者総合支援法 | ・施設や精神科病院に入所している障がいのある方で、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方 | 地域移行に支援が必要な方に対しての移行支援や、地域生活を継続していくための支援を行う | 移行:0.8%
定着:-0.4% |
| 計画相談支援 | 障害者総合支援法 | ・障害福祉サービスを申請した障がいのある方または障がいのあるお子さんで、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められている方
・地域相談支援を申請した障がいのある方で、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた方 |
障がいのある方の自立した生活を支え、障がいのある方の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する | 5.3% |
| 障がい児相談支援 | 児童福祉法 | 障害児通所支援を申請した障がいのあるお子さんで、市町村から障害児支援利用計画案の提出を求められた方 | 障がいのあるお子さんとその家族の生活を支え、障がいのあるお子さんの抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する | 3.8% |
※各支援の対象者について、詳細は厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」をご覧ください
※収支差率には「物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金収入」を含みません。
(参考:厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」)
(参考:厚生労働省「令和 5 年障害福祉サービス等経営実態調査結果」)
基本相談支援とは
基本相談支援とは、市町村が主体となって実施している「地域生活支援事業」の一つです。
障がいのある方やそのご家族が抱えているあらゆる悩みに対して、福祉制度の紹介や情報提供、各種サービス利用のサポート、権利擁護、緊急時の対応など、地域生活全般の相談支援を総合的に行っています。
後述する地域相談支援や計画相談支援といったサービスにつながる前段階に位置しており、最初になんでも相談できる窓口としての役割を担っています。
地域相談支援とは
地域相談支援とは、主に施設や精神科病院に入院している方が、退院・退所後に地域生活を始める場合や、その後地域生活を維持していくことのサポートに特化した支援です。
この支援には以下の2サービスが含まれています。
地域移行支援
入院・入所中から退院・退所を見据えて、住居の確保や地域のサービス調整など、退院・退所後にスムーズに地域生活へ移行するための支援を行います。
地域定着支援
地域生活に移行したのち、緊急時に必要なサポート(24時間連絡体制など)を提供し、地域での生活を維持し孤立しないように地域生活への定着をサポートしています。
計画相談支援とは
計画相談支援とは、居宅介護や各種施設入所など、各障害福祉サービスを利用する成人の方を対象に、その利用計画作成のサポートをしたり、管理したりする支援です。
計画相談支援には以下の2サービスが含まれます。
サービス利用支援
障がいのある方ご本人やご家族の意向をヒアリングし、どのようなサービスをどれくらい利用するかを定めた「サービス等利用計画案」を作成します。
また、この計画案をもとに市町村への支給申請のサポートを行います。
継続サービス利用支援
サービス利用開始後、少なくとも6か月に一度、計画の見直し(モニタリング)を行います。
モニタリングを行うことで、計画が利用者本人の生活にあっているかを継続的に評価し、必要に応じて計画を適切なものに改善・変更します。
障害児相談支援とは
障害児相談支援とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する、障がいのある18歳未満の方とそのご家族を対象にした支援です。
この支援には以下の2つのサービスが含まれています。
障害児支援利用援助
ご利用者の状況やご家族の希望にもとづいて、適切な障害児通所支援サービスを組み合わせ「障害児支援利用計画案」を策定します。
作成した計画案をもとに、市町村への支給申請もサポートしています。
継続障害支援利用援助
障害児通所支援サービスの利用開始後、少なくとも6か月に一度、計画の見直し(モニタリング)を行います。
定期的な計画の見直しを行うことで、元の計画が適切かどうかを都度評価し、計画を最適化していきます。
まとめ
ここまで、各「相談支援事業」が持つ役割や内容、それぞれの事業を担う「事業所」の種類、そして提供されるサービスの関係性について詳しくご紹介してきました。
相談支援事業は、障がいのある方々が地域で自分らしく生活を送るために、非常に重要な役割を果たしています。
この事業が、計画相談、地域相談、障害児相談という3つの専門的な柱で構成され、それぞれ特定・一般・障がい児相談支援事業所によって提供されていることをご理解いただけたかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
開業に関する資料をダウンロード
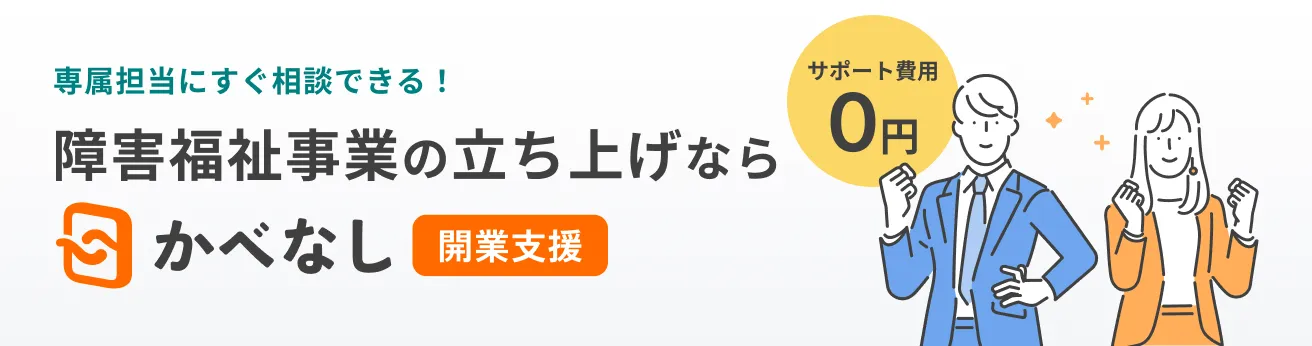

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。