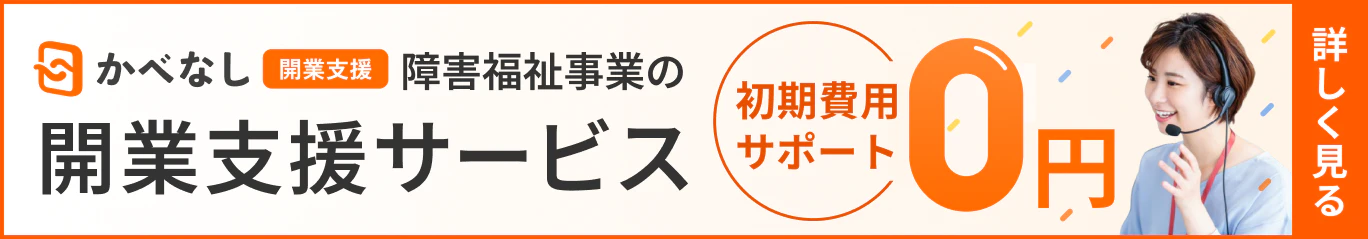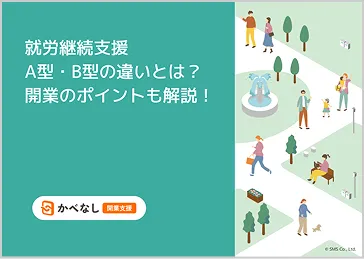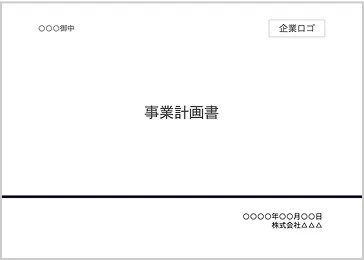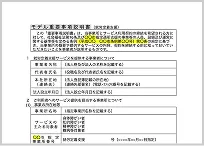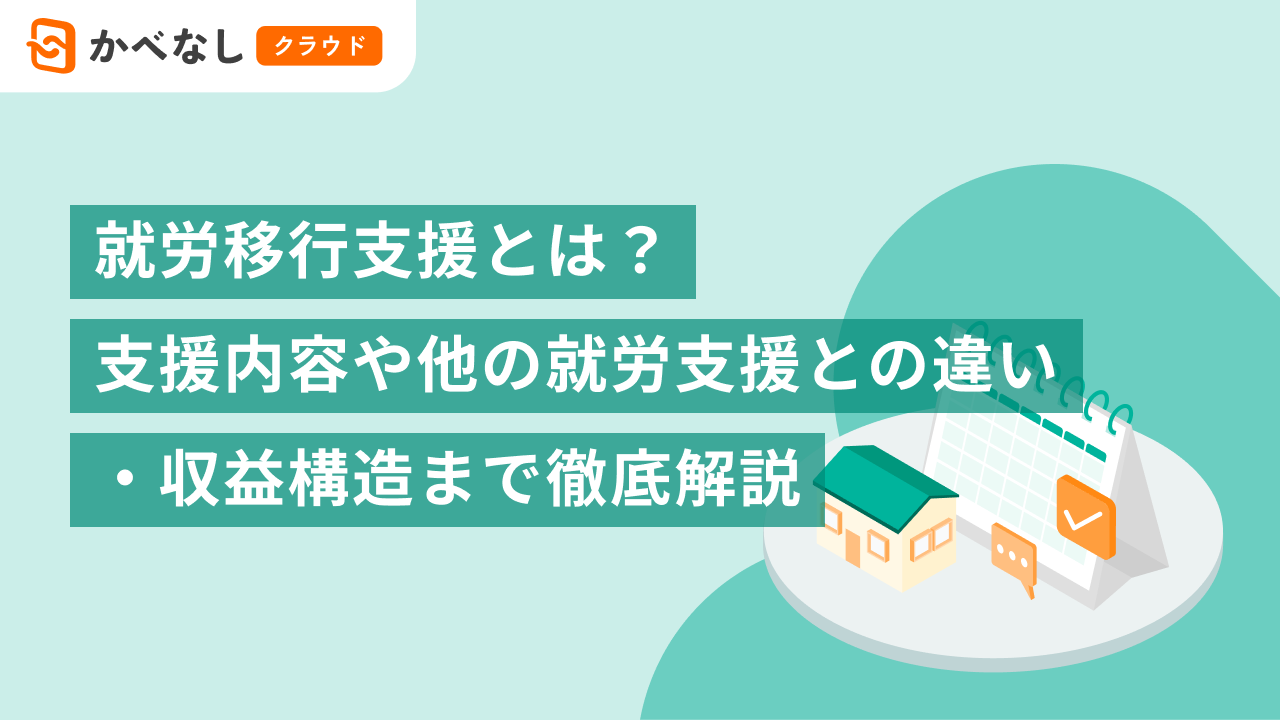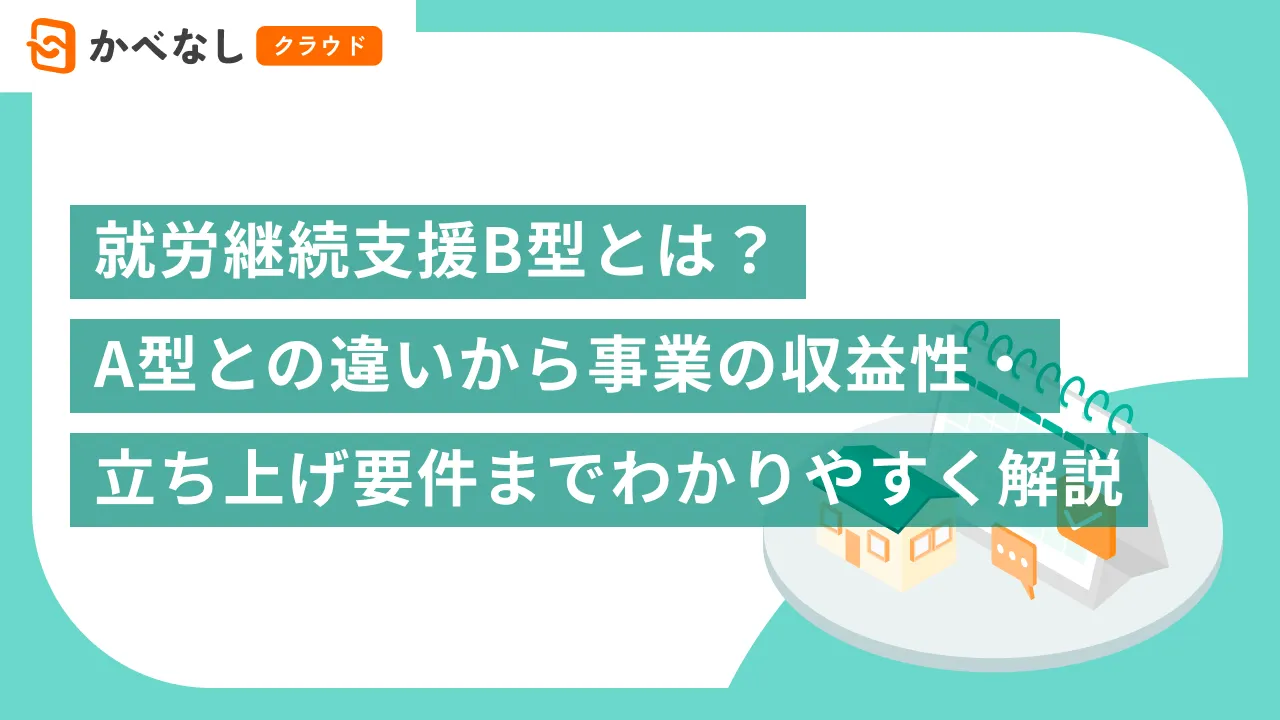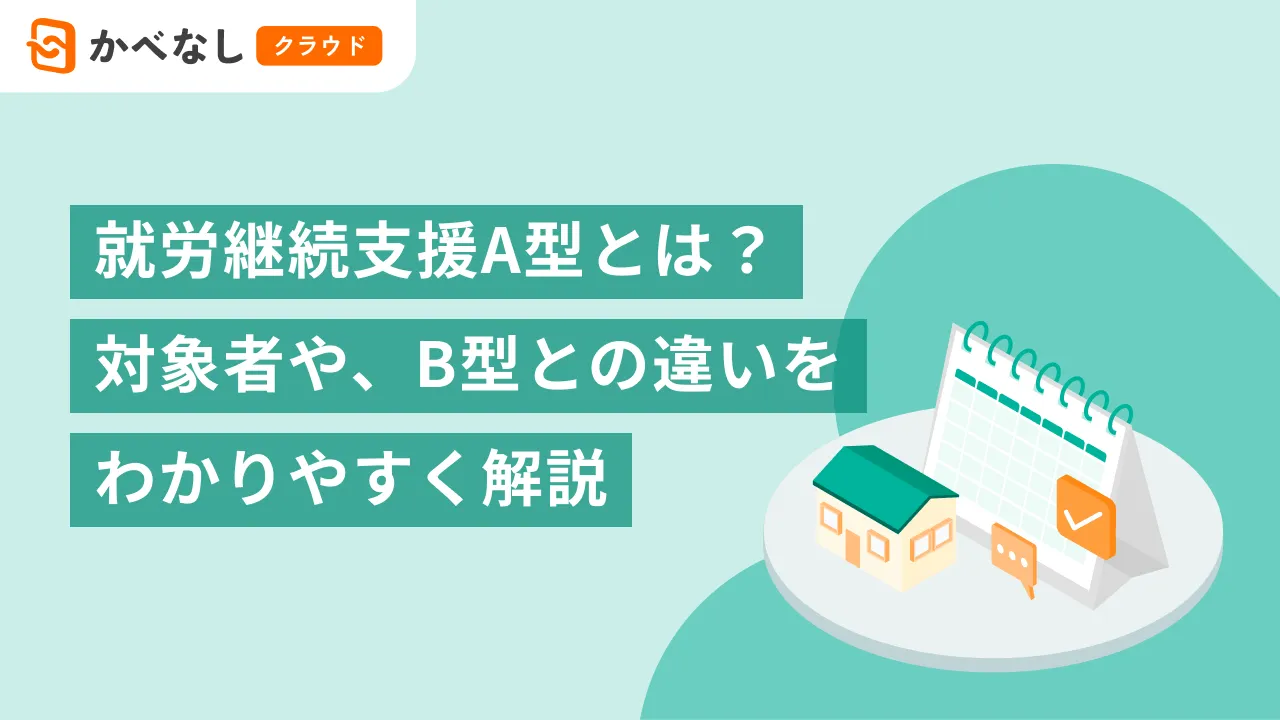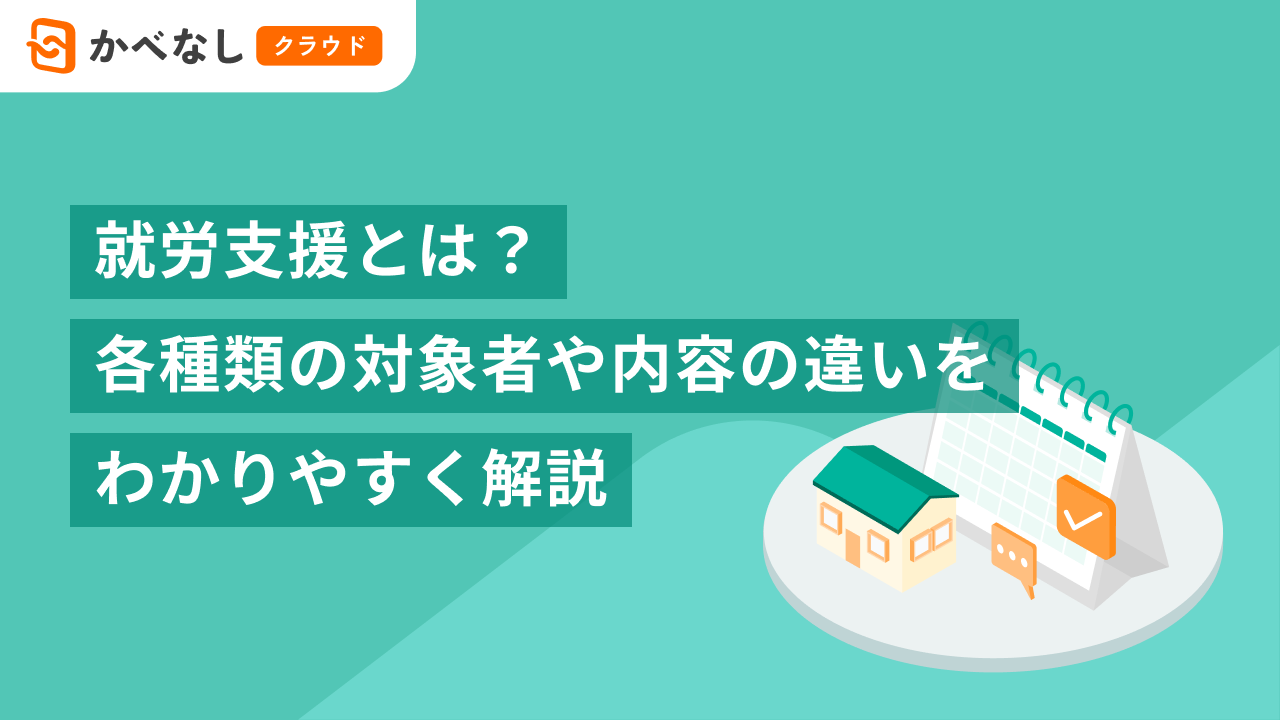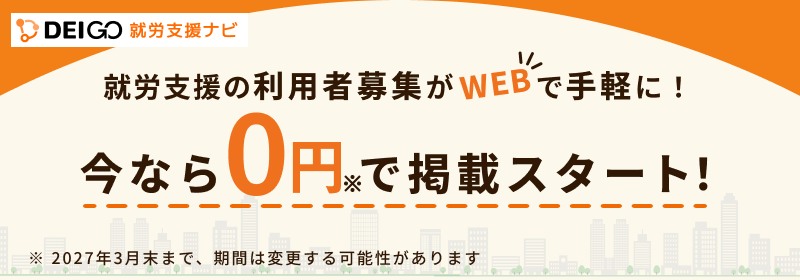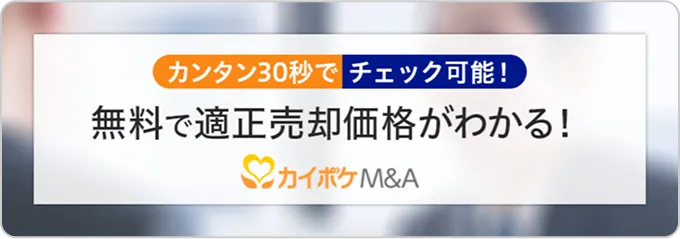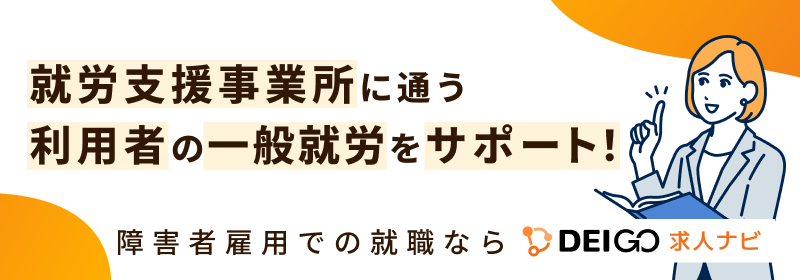障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
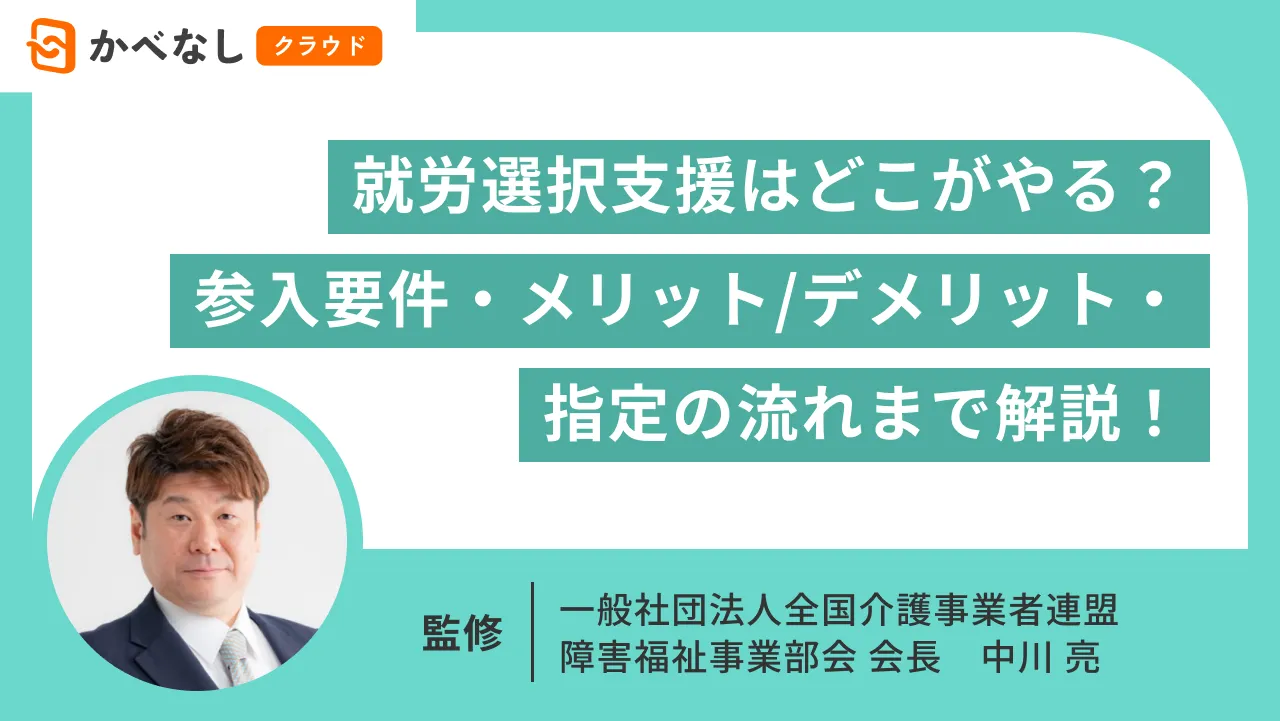

日本福祉コンサルティンググループ株式会社 代表取締役社長
障害福祉事業所14000以上が参画する(一社)全国介護事業者連盟障害福祉事業部会 会長。コンサルタントとしても全国700以上の事業所設立、1000以上の運営支援にも携わる。厚生労働省やこども家庭庁の検討会にも参加し、利用者と職員双方の満足度の高い施設作りに尽力している。
令和7年(2025年)10月から始まる就労選択支援について、就労系サービスの経営者や開業を検討されている方は、「就労選択支援はどこがやるのか?」や、「就労選択支援は新たな事業機会になるのか?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
今回は、基本情報から、事業としての可能性や参入メリット・デメリット、指定の流れまでを実務目線で整理します。
就労選択支援はどこがやる?
就労選択支援を実施できるのは、既存の障がい者向け就労系サービスを運営する事業者のうち、一定の就職実績を満たすところです。
対象となる事業種別の一部
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援A型事業所
- 就労継続支援B型事業所
事業者の要件(原則)
原則として以下のどちらかの就職実績があると、就労選択支援事業者と認められます。
- 要件①:過去3年以内に3人以上の利用者を一般企業等へ就職させた事業者
- 要件②:上記と同等の経験・実績があると都道府県知事に認められた事業者 (例:障害者就業・生活支援センターの受託法人、自治体設置の就労支援センター など)
例外・特例(地域事情への配慮)
同一市区町村内に就労選択支援事業所が存在しない等の事情がある場合、評価期間を長く取った実績(例:過去10年間の連続する3年間で合計3人以上の一般就労実績 など)を知事が同等実績として認める運用が想定されています。
※詳細は各自治体の運用通知で最終確認してください。
就労選択支援事業の基本情報について、下記の記事でもまとめています。
就労選択支援の前提と実情(令和7年9月1日現在)
就労選択支援は、まず就労継続支援B型事業所の利用を考えている方を対象に始まり、令和9年4月からは就労継続支援A型を新たに利用する意向がある者、就労移行支援を既に利用しており更新の意向がある者にも対象が広がります。
令和6年報酬改定前からの厚労省障害者部会や報酬改定検討チームでの議論から、当初、就労選択支援のスタートによりB型事業所の利用者受け入れまでの流れはかなり厳格化されると考えていました。しかし、令和7年3月31日の厚労省の通知で、事業所側はこれまでの就労継続支援B型の受け入れの流れと大きな違いはないという整理になりました。
それでも、サービススタート1ヶ月前の9月上旬の段階で、想定より新規開業は少ないのが実情です。その主な理由として、就労選択支援の人員配置に必要な専門的な人材の確保が難しいことや、サービスに関する情報がまだ十分に浸透していないことが挙げられます。
例えば、愛知県名古屋市には約400の就労継続支援B型事業所があるのに対し、就労選択支援の申請は10事業所にとどまっています。また、事業所の指定基準(建物基準など)が指定権者の解釈によって異なることも、普及を妨げる一因となっています。
就労選択支援事業は儲かるのか?
報酬は「就労選択支援サービス費」=1日あたり1,210単位(基本)です。
提供日数と利用者数の積み上げにより売上が決まる単位制です。前提条件(対象者数、提供日数、人員コスト、移動・連携コスト)次第で収支は大きく変動します。
また、加算の取得や減算に注意することで事業の収益性を高めることができます。ここでは、就労選択支援で注意すべき減算をご紹介します。
注意すべき減算:特定事業所集中減算(200単位/日)
就労選択支援では、利用者が特定の法人へ集中して移行した場合、「特定事業所集中減算」として1日あたり200単位が減算されます 。集中率は次式のイメージで把握できます。
集中率 = (評価対象期間に“移行率が最高の法人”につながった人数) ÷ (同期間に就労先へつながった総人数)
減算の対象となるのは、自社の就労支援事業所への移行率が80%を超えた場合のみであるため、大きな影響はないと考えられています。
就労選択支援で収益を最大化するポイント
事業所の多くが、管理者兼就労選択支援員の1名配置での運営を考えているという声があります。一方で、自治体は2名程度の配置を見込んでいる状況です。
受給者証は1か月の付与ですが、利用者が全日利用するわけではなく、アセスメント終了後10日〜2週間で就労支援へ移行するケースが多いと見込まれます。つまり、契約者数を増やし1日の利用者稼働率をいかに上げていくかが事業成功の鍵になります。
収益を最大化するには、以下の点に注意する必要があります。
- 候補先を複数提示する
- 利用者本人の意思決定を尊重する
- 紹介や合意内容を徹底して記録する
- 地域の複数の事業所や企業と協力して実習を計画する
- 月次ダッシュボードで移行先の偏りがないか監視する
利用者数が少ない事業所や、利用が少ない地域では、就労選択支援そのものから利益を出すのが難しい場合があります。
その場合は、自社グループや提携している事業所に利用者を移行させることで、就労支援事業所の利用者確保や売上確保を主な目的として運営することが考えられます。
就労選択支援事業参入のメリットとデメリット
就労系サービスを経営している方や開業を考えている方は、就労選択支援の参入に迷われている方もいるのではないでしょうか。就労選択支援に参入する際のメリットとデメリットを把握しておきましょう。
就労選択支援事業参入のメリット
就労選択支援は、障害のある方が自分に合った仕事を見つけるのを助けるための新しいサービスです。この事業を始めることには、主に4つの利点があります。
①支援の質と利用者満足の向上
利用者の就労に関するニーズを詳しく把握し、多角的なアセスメントを行うことで、ミスマッチの少ない就職を促し、その後の定着にも良い影響を与えます。結果として、利用者の満足度が上がり、事業所全体の支援の質や実績が向上します。
②新規ニーズへの対応
このサービスは、これまで十分にカバーされていなかった「就労先を選ぶ」という新しいニーズに応えるものです 。令和7年10月から段階的に導入されるため、需要の増加が見込まれており、早期に参入することで市場での優位性を確保できます。
③包括的支援での効率化
すでに就労移行支援や就労継続支援A型や就労継続支援B型の事業所を運営している法人は、就労選択支援を多機能型事業所として統合することで、人員体制や設備を共有でき、運営コストを最適化できます。
④地域連携の強化
このサービスを通じて、相談支援事業所、企業、医療機関など、様々な関係機関との連携が深まります。これにより、地域社会における信頼性が高まり、事業所の存在感も向上します。
就労選択支援事業参入のデメリット
一方で、事業参入には以下のような課題も伴います。
①専門人材の確保と育成が難しい
就労選択支援員には、就労に関する専門的なアセスメント能力や、多様な就労選択肢に関する情報収集・提供能力、利用者や関係機関との連携調整能力などが求められます。これらを兼ね備えた就労選択支援員の配置・研修・OJTに時間とコストがかかります。
就労選択支援員になるための就労選択支援員養成研修については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
②客観性・中立性ルールの遵守
令和7年10月から始まる新しいサービスということもあり、自治体でのローカルルールや自治体間での齟齬が想定されます。
③既存事業のオペレーションの見直し
既存の就労系サービスと同一事業所内で就労選択支援を提供する場合、時間帯や空間の分離、他事業所との連携プロトコルづくり等、導入時の調整が必要です。
就労選択支援の指定の流れ(東京都の例)
就労選択支援事業を始めるために必要な準備や手続きを紹介します。ここでは、東京都の流れを例に紹介します。事業を開始する都道府県・市の案内を確認しましょう。
① 実施要件と体制の整備
指定申請の前に、以下の内容を確認しましょう。
- 目的・理念
- アセスメント環境(手法、作業場面、シート・マニュアル)
- 過去の就労支援実績
- 地域連携の状況
- 第三者評価
- 情報公表(WAM-NET等)
② 申請書類の提出:期日までに窓口へ提出しましょう。
主な様式は次のような書類です。
- 指定申請書
- 体制一覧
- 勤務形態一覧
- 就労選択支援員の研修修了証
- 登記事項証明書
- 事業所平面図と面積表
- 設備・備品一覧
- 経歴書・実務経験証明
- 運営規程
- 協力医療機関
- 関係機関連携の議事録 など
③ 申請書類の審査
東京都福祉保健財団が審査します。必要に応じて指定前実地調査(現地確認)を実施します。
④ 現地確認(概ね指定前月の中旬)
基準適合、受入体制、備品・動線等を確認します。
⑤ 指定通知書の交付
指定年月日以降に事業開始可能になります。
※ 指定の様式・要件は自治体で異なります。最新の案内で最終確認してください。
就労支援事業の開業をかべなし開業支援がお手伝いします!
就労支援事業の開業には、半年から1年ほどの準備期間が必要です。
『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。
「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集だけでは抜け漏れがありそうで不安だ」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度『かべなし開業支援』の資料をご請求ください。
まとめ
就労選択支援の事業者要件から、事業としての可能性、参入メリット・デメリット、指定申請手続きまでを概観しました。
就労選択支援事業は、要件と中立性を押さえ、地域連携を前提に準備を進めることが成功の鍵です。不明点は自治体の最新案内で確認し、実装は“記録の一貫性”と“本人中心”から!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
開業に関する資料をダウンロード
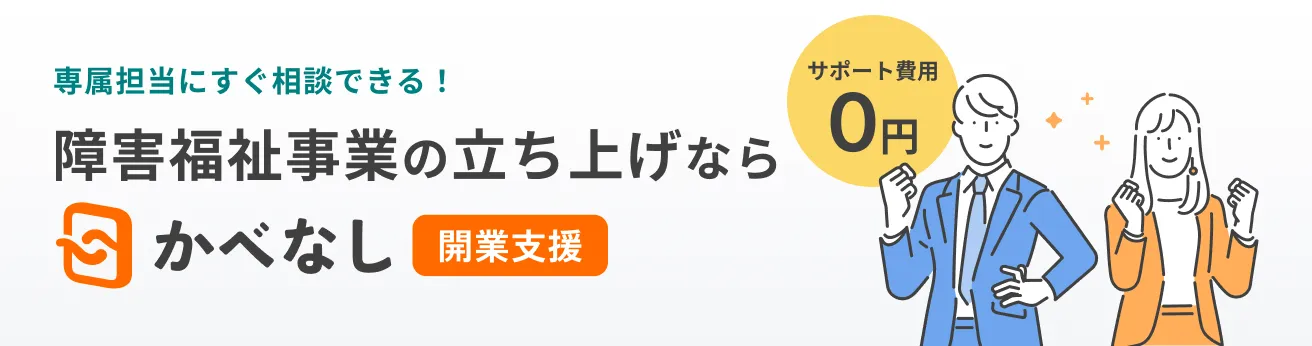

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。